「インターネット」
村井 純著 岩波新書①1995
岩波新書新赤本800点の中から、3人の座談会「新書の役割」「新書への期待」で推薦されていた。その中に「この本はインターネットという仕組み、考え方の基本が何なのかをはじめて書いた本」「理科系の人ならインターネットを使えないということはありえないでしょうね。」などとある。
著者は、1955年生まれ。現在、慶応技術大学環境情報学部教授で、インターネットを育て、方向付けされ、現在、第1人者として活躍中。
インターネットの仕組みは大変簡単
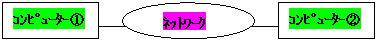
- コンピューターを繋ぐネットワーク
- 双方向の通信ができる
- 高速、大量に(デジタル情報を)扱える
- 国境がなく、1秒で地球を1周出きる
⇒人間のコミュニケーションの特徴である「双方向性」、「対等性」、「日常性」を持っている
仕組みの特徴
- 到達性と冗長性:鉄道と同じで到達はできるが、回り道をすることがある。
- 新設コストは大変少ない。⇒従量料金から固定料金になるべき
- 信頼性と全体の強靭性がある
- 大変簡単な技術。いい加減な技術の集合である。
*ラフなコンセンサスで90%までは比較的簡単に進め、残りは必要な時に積めていく方式で大体上手くいくので、急速に広がっていく。
どのように使えるか:インターネットは現代の百科辞典
- アドレスとネームで識別する。
- 電子メール:1つの革命的なコンピューターの応用。
*ファイル転送(添付文書)やメーリングリスト(グループ間の情報交換)も使える。
- 情報検索:(キーワードを入れるだけ)や関係先へのリンクで次々繋がり、検索できる。
*WWW、URL、HTMLなどから今後は電子貨幣などへ
何時でも繋がることが特徴。
ダイアルアップ接続は狭い意味でのインターネットには入らない。
インターネットの可能性は
- イーサネットを筆者はハワイ大時にで考えたが、統計的に考えて繋ぐもので、この考えが実用になった。
- 電子メール:他者との共有や再利用、加工が自由。
- 双方向性を活用すると新ビジネス、雇用に発展する。
- 言語は、英語だけでなく、日本語などそれぞれの言語が基本。
*日本では、電話の固定料金のしくみでは、回線料金はべらぼうに高く、1985年にNTT民営化後、回線が安く利用できるようになってようやく発展。
課題と展望
個人の視点を共有し、普遍性を持ったものになる。モーバイル化も進み、料金も大幅に低減する。セキュリティについて心配する向きも多いが、技術はできており、電子署名もできる。
⇒子供の頃から使い、地球上どこでも自由に使えるものになるし、エチケットやモラルは段々合意・形成される。
コメント
2002年末にADSLなど常時接続が700万台を超えた。また、いつでもどこからでも使用できる「ユビキタス」という概念が一般化しつつあるなど、現在で通信料は100分の1程度になり、1995年に書かれた本書の内容が実感できるようになった。専門技術者の洞察力は驚くべきものである。なお、筆者は1998年に「インターネットⅡ」を同じく岩波新書から発刊している。