���� 2023�N1��14�� ��V���|�W�E���̂��ē� ����
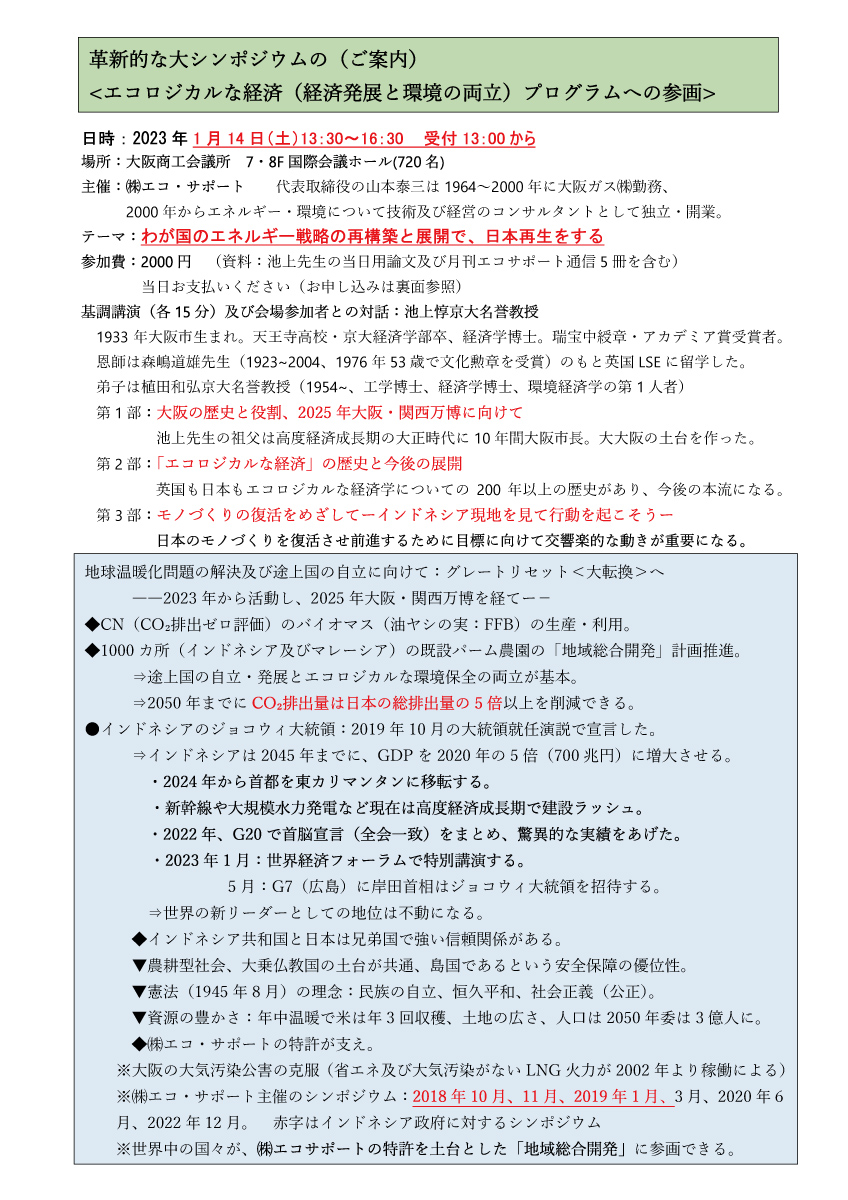
>> ���ē���PDF�o�[�W�����͂�����
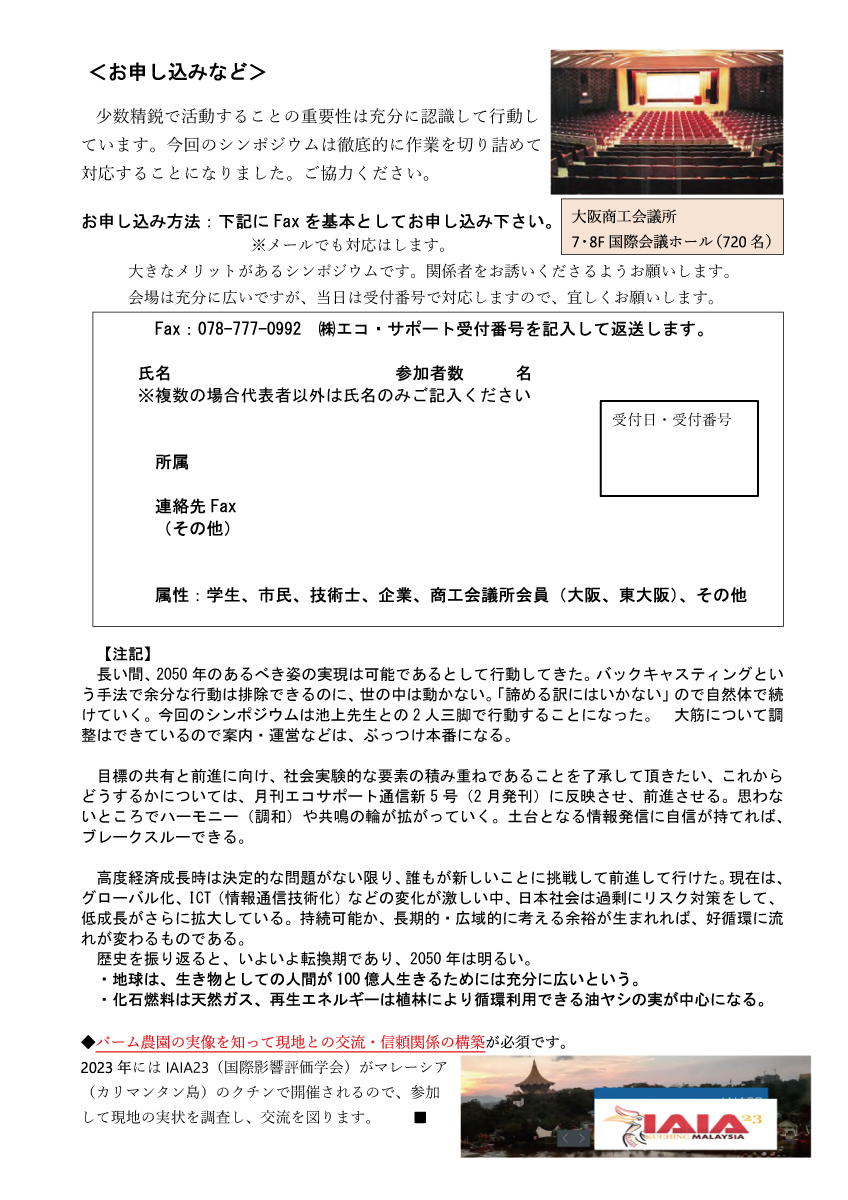
>> ���ē���PDF�o�[�W�����͂�����
2020�N7���P���X�V �@�@�@�@�U��26���V���|�W�E���̌��ʁ@
�V���|�W�E���͐���ɏI�����A�u��錾�v���S���v�ō̑�����܂����B
����̊����ւ̑傫�ȑ����ɂȂ�܂����B
8�����{�ɂ́AA4�Ŗ�100�y�[�W�̕����쐬���A�����̎Q���҂ɗX�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@��@���@
������ЃG�R�E�T�|�[�g�́A�����J���^�R���T���E�V���N�^���N�Ƃ��ė����̃p�C �u�����ʂ����A
1�D�C���h�l�V�A�̎���(�A�u�����V)����{�̋Z�p�ŁA�����āA�����̘A�g�E���͂� ����
�@ �d�́E�R�����J���̐��i���͂���B�@
2�D2050�N�����āA���������E�ɐ�삯�Čo�ϓI?�����I?�����\�Ȓn�����g����ւ�
�@ ��������B�@
3�D�p�[�є_���ɓK�p����V�������ۓ����̎��{�����C���h�l�V�A���{�ɖ����� ���A
�@���̎��ƂɊւ���v���b�g�t�H�[�����\�z����B�@
4�D�C���h�l�V�A�̃W���R�哝�̂���N1�Z���ɏA�C�����A�Ɨ��錾��1�Z�Z���N��
�u2045�N�ɂ�GDP���E��5�ʈ�?��ڎw���v�Ɛ錾�B���̎����ɂ͓��{�̌o���ƋZ�p��
�K�{�ƔF������B
5�D���{�ƃC���h�l�V�A��2050�N�ȍ~�ւ̋P�������������邱�ƁA���̓������g�傷��
�����̏d�v�������Ɋm�F�����B
�ߘa2�N(2020)6��26���@
������ЃG�R?�T�|�[�g�@
������@���������@�쐬�@
2020�N6��18��/25���X�V �@�@�@ �U��26���V���|�W�E���p
���Q���\���F�@HP�u�G�R�T�|�[�g�ʐM�v����Bhttps://www.eco-support.co.jp/
�@�@�@�ˁw�G�R�T�|�[�g�ʐM�x��HP�ɓ������獶���A�ڎ��́w�g�b�v�y�[�W�x���N���b�N�B
�@�@�@�@�V���|�W�E���ē��E�֘A�L���̍ʼn��i�ɂ��\�����݂ɂ��ċL�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�Q����F2000�~�@�W�����{��A4��100�y�[�W�̕���X�����܂��B
�@�@�@�@�\���p���[���Ɏ���,���������L�����������B�Fdfaqv509@kcc.zaq.ne.jp
�@�@�@�@�����A�֘A���M���A����ɂȂ莟��A�\���E�L�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@��
�z�[���y�[�W�̍ĊJ�ƃV���|�W�E���̊J�Ái���ē��j
2012�N�P��14���ɋZ�p�m���������ÂŃZ�~�i�[���J�Â��Ĉȗ�8�N���o�߁B�킪���̒����I�ȃG�l���M�[�헪�̎��s�E���i���K�v�ł��B2013�N�Ɋ�������ϑ��������d���Ɛ��i����ł̓��\�͊�,���p�݂ɓV�R�K�X�ɂ���i�^�̉Η͔��d���̌��݂ł��B���Ђ����Ƃ��p�����A���{�ł̎��g�݂ƂƂ��ɊC�O�Ɏ�����L���Ċ������Ă��܂��B
���̌�̎�g�݂͏����ŁA2050�N�̒n�����g����ւ̓������m�ɂȂ����܂��B�C���h�l�V�A�̃p�[���_���łł���c��ȃA�u�����V�̉ʎ��iFFB�j�d�E�R�������邱�ƁA���{�ƃC���h�l�V�A���A�g�E���͂��ēd�́E�R�����J����i�߂邱�ƂŁA�����͐��E�ɐ�삯�Čo�ϓI�Ō����I�Ɏ����\�ȉ��g����������\�ł��B
�C���h�l�V�A�̃W���R�哝�͍̂�N10���̏A�C�����œƗ���100���N�́u2045�N�ɂ�GDP���E��5�ʈȓ���ڎw���v�Ɛ錾���܂����B���j�I�ɂ��n���w�I�ɂ����{�ƘA�g�E���͂��d�v�ł��B���{�ł͖w�ǒm���Ă��Ȃ��C���h�l�V�A�̃p�[���Y�Ƃ��܂߁A2020�N���ɍ��̐���Ɉʒu�t������悤�A�ȉ��̎�g�݂�i�߂܂��B�����́E���x�������肢���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ЃG�R�E�T�|�[�g�@��\������@�@�R�{�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L
�P�D��ʎВc�@�l�G�l���M�[�E�����w���39�����\��(7��28���`29��)�ɓ��Ђ���4���̘_���\���A���̌�@�֎��Ɍf�ڂ��邽�߁A���e�葱����6��15���Ɋ������܂����B
�Q.�@6��26��(��)�ɓ���㏤�H��c���œ��Ў�ẪV���|�W�E�����J�Â��܂��BHP�u�G�R�T�|�[�g�ʐM�v�ɖ����֘A�̏d�v�����f�ڂ��āA�Q���ē������܂��B
�R�D��L�̊������ʂƂ��āA�����W���P���ɍ쐬���\���܂��B2012�N����̎�g�݂ƐV�^�R���i�E�B���X�̏o���헪�Ɋւ�锭�\���܂݂܂��B�R�ĉȊw�E���w�E�H�w����̗ގ����ɂ��Ă̍l�@�Ǝ��H�����ł��B
�S�D�P�Q�����ɒn�����g���Ή��̓����A�L�������O�ɗ������ꐭ��ɔ��f�����悤�o�ł�ڎw���܂��B2050�N�Ɋ���l�X�ɑ��đ傫�Ȗ��������鏗�����d�v�ȖڕW�ł��B
5�D�����̕����ǂ�Ŋ����x���������߂̏o�łł��B�R�{���L�̊���(���{��4000���~)�̈ꕔ���z�ʂł����������A�������m�ۂ��܂��B�ʓr�A�����͂����肢���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�@���@
2020�N6��21��
�p�[���Y�Ƃł̎����E�n�敪�U�^�d�͐��������V�X�e���@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�p�m�i���݁A���A�q���H�w�A�����Z�p�ė��j�@������@��F�@
�P�D�C���h�l�V�A�ƃv�����e�[�V����
�@��N10���A�C���h�l�V�A�̃W���R�哝�̂͑�2���̏A�C���ŁA�u�C���h�l�V�A��2045�N��GDP���E5�ʈȓ���ڎw���v�Ɛ錾�����B�A���n���ォ��v�����e�[�V�������������̊�Y�ƂɂȂ��Ă���A�p�[���Y�Ƃ����ƂɊ֘A�Y�Ƃ��g�傷�邱�Ƃ��Ӗ�����B
�Ɨ���A�v�����e�[�V��������Ɍo�c�����̂́A�A���n����Ɏ�����S�����Ă��������l�̎��ƉƂ����ł���B�͔|�앨�͈ꎟ�Y�i����V�R�S���тɈڂ�A�Ɨ���͐��Y���E���v���̍����A�u�����V���͔|���A�ʎ����瓾����p�[�������吶�Y���ƂȂ����B�p�[���_���̃C�m�x�[�V�����Ɋւ��ẮA���{��������i��肵�Ȃ��Ă��A�p�[���_�����Ǝ�̖L�x�ȍ��ۏ��Ǝ��{�Ői�߂邱�Ƃ��\�ł���B
�Q�D�A�u�����V�@
�@�A�u�����V�͔M�щJ�тł̂ݐ��炷����ł���B�v�����e�[�V�����͔̍|�ł�3�N�ʼnʎ������n����B20�N�ŊF�����A�Ւn�ɕi����ǂ����c��A�т���B�_����20�N��1�T�C�N����]����悤�u���b�N����Ōv�悷��ƁA�ʔN�G���h���X�ʼnʎ����n���\�ł���B�@
�@
�R�D�p�[����
�@���m�̊�Ƃ𒆐S��RSPO�u�p�[�����̎����\�ȃp�[�����̂��߂̉~���c�v��ݗ����ARSPO�F�؎擾��Ƃ������A���ۓI�{�C�R�b�g�^���ɂȂ��Ă���B�p�[�����͍��ۓI�ɐH�����Ƃ��đ哤�Ƌ������Ă��邪�A�哤�͑��A�A�u�����V�͎��Ȃ̂ŁA���Y�����ł̓p�[�������D�ʂł���B
�ʎ��̐��Y�ʂ̈��萫�������̂ŁA�����I�ɂ݂�Ǝs��o�ς𗐂��H���������R�������K���Ă���B�p�[�����Ɋւ��A�H��������CO2�[���]�����Z�R�����ւ̃p���_�C���]����}�邱�Ƃ́A���ۓI���n�����2030�N��SDG���ڕW�A2050�N�̃p������ڕW�ɉ����Ă���B�C���h�l�V�A���{�ł́A���肵�ċ����\�ȃp�[�����̔R���������̊�{�헪�A�o�ϔ��W�̌����͂Ɉʒu�t���Ă���A����͖{�C�ł���B
�S�D�����E�n�敪�U�^�d�͐��������V�X�e���@
�@���݁A700��������p�[���_���������^�Œn�敪�U�^�̔��d���ɂ��A�p�[���_�����q���o�ϓI�Ȏ��Ɨp�d���̃l�b�g���[�N���\�z����B���̓d�͋����l�b�g���[�N����������邱�Ƃɂ��n��J�����i�݁A�p�[���_���͑��������ɔ{�����A�W���R�哝�̂̍\�z�͎����ł���B
�T�D���ۓ����ƃv���b�g�t�H�[���@
�@�G�R�E�T�|�[�g���o�^���Ă��鍑�ۓ�������ɁA�p�[���_���ɓK�p����V�������ۓ�����2020�N3���ɐ\�������B���̎��{�����C���h�l�V�A���{�ɖ����Œ���Ɩ��Ă���B���̎��ƂɊւ���v���b�g�t�H�[������ɓ��{�ō\�z����B�C���h�l�V�A���̓e�����[�N�ŎQ�����邱�ƂɂȂ�B
�@700�����̃p�[���_�������A�d�͐��������l�b�g���[�N�����鎖�Ƃ́A�����^�Œn�敪�U�^�̗��z�I�ȃG�l���M�[�C���t�������������ł���BCO?�r�o�[���]���̍Đ��\�G�l���M�[�����肵�ĉi���I�ɐ��Y���邱�ƂɂȂ�A�v���b�g�t�H�[���ɎQ��������Ƃ́ASustainable�Ȏ��ƂƊւ�邱�ƂɂȂ�B
�@�����̑g�ݗ��ĂƃC���h�l�V�A�Ƃ̋��c�́A�m�[�x���o�ϊw�܂����܂����X�e�B�O���b�c�����i�č��j�̃��[�j���O�E�\�T�C�G�e�B�u��������Љ�v�̍l�����ɉ����Đi�߂邱�ƂɂȂ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
2020�N6��22���@
��������S-GTCC �iSustainable Gas Turbine Combined Cycle �j���d�V�X�e���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�p�m�i�q���H�w�j�@�[�c�@�W��@
�P�D�������Ŏ����\��GTCC �iS-GTCC�j�@
�@�R�ăK�X�ʼnғ�����K�X�^�[�r���iGT�j���d�@�ɉ����A�^�[�r�����o�����600�`700���̔r�K�X������C�����ғ�������C�^�[�r���iST�j�Ŕ��d����GTCC�iGas Turbine Co��bined Cycle�j�̋Z�p��1985�N�ɂ͓��d�x�ÉΗ͂ō��v500��kW�Ɛ��E�ő�K�͂ō̗p���ꂽ�B���̌�̋Z�p�J���͔��d�����̌���̂��ߑ�K�͉������ݖ�60%�ɒB���Ă���B
GTCC��Zero Waste�̍l�����ŁA�����A�b�v��ڎw�����V�X�e����S-GTCC�Ɩ��t�����B
�i�P�j�r�K�X��NOX���[���ɂ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�˃p�[���_���ł͉��˂��s�v
�i�Q�j�r�K�X���̐����C���M����ɂ��M�����̌���@�@�ː����C�ɂ��i�ϑ���s�v
�i�R�j���M����ɂ���������N���[���Ȑ��̗L�����p�@�ˏd�v�ȃC���t���ɂȂ�
���ɂ̍������V�X�e���ł���A�C���h�l�V�A���̃p�[���_���ł̍œK�V�X�e���ł���B
�Q�D���{�ł̊J���o��
�@1998�N�ɑ�C������肪�A�ł��[���ȑ��s���ł̐V�݂�15��kW�͏]��������I�ɍ����E�ɋZ�p���̗p�����B�s����s��������K�v�Ȕ��d���Ƃ��č����]�����ꂽ�B�ő�̎�v�҂͊��d�͂ł���B��������A��B����̐ΒY�A���̌�C�O�̐Ζ��ɕς������d����2002�N�ɔp�~�����BS-GTCC�ł���A���A�Z�X�����g���ȑf�����邢�͕s�v�ɂȂ�B
�@2011�N�̕����������̂̌�A2014�N�ɂ͑��̖��F�ŁA�������e���]���@�̑�1���Č��Ƃ���LNG�ɂ��S-GTCC��^���d�v����������o�ώY�Ƒ�b�̈ӌ������\���ꂽ�B�������A���Ǝ҂����X�N���Ƃ��ċ�̉����Ȃ��B2016�N6���̍��ۉe���]���w��IAIA16�Ŋ����E�ɐG�}��p����NO�I��99%�����ł��邱�Ƃ����������S�ƕ]�����B
�@2017�N�ɍ����K�X���Ǝ҂Ƃ̊Ԃ�5000kW��S-GTCC�̎��،�����GTCC���o�ϐ����������������A���v���������ƃV�X�e�������x���Ⴍ�ێ��Ǘ�������ŕ��y���ɂ����B
�R�D�p�[���_���ł͓d�̓C���t�����_��ɍ\�z�\
�@�p�[���ʎ��iFFB�j������C�𗘗p���ăp�[���e���iCPO�j���������������ƁA��������̔p�t�iPOME�j���甭������o�C�I�K�X��60%���x�̃��^���iCH?�j���܂�ł���B�C���h�l�V�A���{�́A�ߎ������o�C�I�K�X�d�p�R���Ƃ��鐭���i�߉��g����h�~����ƍ��ۖ����B�o�C�I�K�X����1MW�i1000kW�j�K�͂̔��d���ł���B���{�̓K�X�G���W���iGE�j���d�̎��ؕ��y�Ɏ��g��ł��邪�A�ۑ肪�����B
�@���̃p�[���_�����Ǝ҂͍����n�ŖL�x�Ȏ����͂�����A�����ȕߎ��ݔ�������70�����ɐݒu�����B���肵��S-GTCC�̐ݒu�E���p���v���W�F�N�g�ɋ����Q��̈ӎv�������Ă���B�p�[���_���ł͋C�̔R���Ɖt�̔R���Ƃ̑g�����ɂ��A�d�͎��v�ʂɉ����ĎY�Ƃ̃R���ł���d�͋������v��I�ɐ��i�ł���B
�@BPPT�i�Z�p�������p���j�����͌��݂���700�J���̃p�[���_���ɂ��ׂ�S-GTCC����{�̋Z�p�������2019�N3���A���ł̃V���|�W�E���ňӎv�\�������B���̉�����ɃW���R�哝�̂̐錾������A����̃A���t�B���E�^�X���t�@�G�l���M�[�E�z��������b�̃��b�Z�[�W�́A���{�������o�������Z�p�̗L���Ȋ��p�ɋ������҂������Ă���B
�S�DS-GTCC�̐��E�I�ȓW�J��
�@�p�[���_���͉��g���J�̔M�ђn��A��������уA�t���J���ŕ��y���i�ށB�o�ςƋZ�p�ŁA�C���h�l�V�A�Ɠ��{�̘A�g�͌������Ȃ��B���т��ł���ƁA���{�y�ѐ��E�ő�^��LNG�ɂ��S-GTCC���d�̕��y���i�ށB2025�N�̑�㖜���̉��͖��F�ł��薢���Љ�̃V���{���ɂȂ�B�C���h�l�V�A��LNG�͊O���l���̗L�͂Ȏ�i�ł���AS-GTCC�ƃZ�b�g�Ő��E�ɗA�o�����y�ł���B���{�̋Z�p����{�l�̂܂��߂��A���P�E���ǂւ̔\�͂Ȃǂ��������A�����ւ̑傫�ȃ`�����X�ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
2020�N6��23��
�K�X���^������̔R�ē����ƐV�^�R���i�E�B���X�̔����I�����Ƃ̗ގ����̈�l�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�p�m�i���A�����Z�p�ė��j�R�{�@�O
�P�D�V�R�K�X�ւ̔R���]���Ə��^��������̔R�ē���
�@1970�N��̍��x�o�ϐ������A�s�s�K�X���Ǝ҂͔R����ΒY�E�Ζ��������Ƃ���s�s�K�X����A���^���iCH?�j���听����LNG�E�V�R�K�X�ɐ헪�]�������B���Ăł͂��łɓV�R�K�X�̃p�C�v���C���Ԃ���������Ă����B�������A���{�ł͓~��̂炢������Ƃ���������鏬�^����������J���E���y���Ă���B�����Ԏg�p����ƁA�_�f�s���ʼn����L�тĔM������ɂ������CO��1���{�ɂ������I�ɔ������A�l�Ԃ̔x�ɓ����ċ}�����Ŏ��̂Ɍq����B
�Q�D��������̔R�Ĉ��S��CH?���p�Z�p�̊g��
�@�V�R�K�X�ւ̐�ւ����A���q�l��̃K�X�������S�ɉ����E�m�F����B�u��Ɏ��̂��N�����ȁv�Ƃ̎В��̖��߂ɋZ�p�ӔC�҂Ƃ��āA����ł̉\�ŗL���ȑ���̗p�����B
�@���^��������̔R�ē����̔c���@�˕]�����ؑ��u�ɂ����������ł̔R�ė]�T�x�̊m�F�@
�A����ł̔R�Ă̔����̐ݒ�Ɖ������i�̎d�l����@�˃��[�J�[����ւ̋��͈˗��@
�BCO���m���[�^�[�̊J���ƌ����Ƃł̎g�p�@��3�Ћ����J���Ŏ����A�����K�X�Ƃ̘A�g�@
�@���q�l�����S�E���S�ŐM�����ċ��͒�����̐����m�������s�����B���K�X�R�Ђ͊e16�N�ԁA���̌�200�Јȏ゠��K�X���Ǝ҂͑S��LNG�E�V�R�K�X�ƂȂ�A�d�͎��Ǝ҂ƂƂ���LNG�͊�G�l���M�[�ƂȂ����B�ł��D�ꂽ���ΔR���Ƃ���LNG�Ƃ��̗��p�Z�p�̌o���E�m�E�n�E�͓��{�ɂ���A���ɂ̔��d���p�Z�p��S-GTCC�̎��A���P�E���y�Ɍq�����Ă����B
�R�D�R���i�E�B���X�Ƃ̕t��������
�@��N11���A�����̕����Ŕ��������V�^�R���i�E�B���X�́A�]���̃C���t���G���U�̃E�B���X���ψق��A���E���Ɋ����g�債���ƍl������B�����͕������͂��ߑS�y�ɔ�ڐG�A2�T�Ԃ̊u���[�u�����A�Z���ԂŊg��������������B���{���܂ߓ���A�W�A�ł��T�˓��l�̑[�u���Ƃ����B�����Ƒ�����Ȃ����ŁA���ɕa�@�W�҂͑�ό�����������������ꂽ�B
�@�E�B���X�́u�זE�̕��q�����w�v�̕���ł̓Q�m����͂�DNA�̍\�����𖾂����ȂNj}���ɐi�������B���ׁA�C���t���G���U�̌����ƂȂ�R���i�E�B���X�i�ȉ��E�B���X�j�́A�ċz�ɔ����l�̔x�̏h��זE�̒��ɓ���ƁA�l�Y�~�Z�I�ɕ�������A�����I�ɑ�C���ɕ��U����Ƃ���Ă���B�E�B���X���ψق��A�p���f�~�b�N�i���E�I���s�j�̔�������������\�z����Ă����B�������A���̔������J�j�Y���Ƒ�ɂȂ��錤����������́A������Ȃ��B
�S�D�V�^�R���i�E�B���X�̔����I���B�E�W�c�����Ə��^���������CO�����̗ގ���
�@�l�Ԃ�100kcal/ha�̔R�Ċ�ł���A�R�ĂɕK�v�Ȏ_�f����荞�ށB�E�B���X������̏������ł́A���Ԍo�߂ƂƂ���1���{�ɂ��������B����ԓ��ɕ��o�����B����̂悤�Ȗ���Ԃɒ����Ԃ���Ɛl���E�B���X������ƂȂ�B��������̎_����Ԃł̔R�ĂƓ��l�ɑ����̊����҂��ł�B�����Ɣ��ǂ̎����̂��ꂪ����A���̃|�C���g���d�_�I�ɁA�Ď��Ǘ����邱�ƂŁA���E�Ɋg�債�����N�Ԃ̑����̒m������\�h�ۑS�̗L�������Ă���B
5�D�E�B���X�̗L���ȏo���헪�ƕ��ʂ̐��������߂����߂�
�@���ʂ̐��������߂����߂ɁA�����̉\�����d�݂Â����Ή�����B�h�C�c�̃����P����5��18���ɍ����Ɍ����Č�������t�͈��S���A�M������^�����B�l�̔x�ɏ\���ɐV�N�ȋ�C����荞�܂��Ɗ����͋N����ɂ����B��Ðݔ�������Ȃ�����n��ɂ��L���ȑA���ʂ̐��������߂���|����ɂȂ�B�o����ɁA���^���ȍ��ŏ��𗬂�}�肽���B
�@��Q�g���N�����Ă������i�K�őΉ��ł���B���O�Ȃ���S�ł���A��s�@��d�ԁA�����o�X�ł����C���\������A���͏��Ȃ��B���ۊԂ̈ړ��ɂ��ẮA�̉�����APCR�����A�����Ԃ̈ړ��ǐՂȂǂ̎��т�ς݁A���X�Ɋɘa���Ă����B�}�X�N�͎������������Ă���ꍇ�̃E�B���X���o�h�~����ړI�ŊO���Ɉ��S����^����B�E�B���X���t�����Ă��Ă��A�ʏ�͊����Ɏ���Ȃ����A���̊����Ǘ\�h�̂��߂Ɏ�Ȃǂ͏K���Â���̂��悢�B�@�@�@��
2020�N6��24��
�y��u���z�@�@�@�C���h�l�V�A�E�p�[�����Y�Ƃ̌���E�ۑ�E����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �_�O�i��@
�P�D�p�[�����Y�Ƃ̌���
�@���E�ōł�����������A�����ł���p�[�����̓C���h�l�V�A�ƃ}���[�V�A�Ő��E�̐��Y�ʂ�85�����߂�B�p�[�������̂��A�u�����V�͌��Y�n�̐��A�t���J�M�щJ�т���19���I���ɓ���A�W�A�ɓ�������C20���I�����ɃC���h�l�V�A�̃X�}�g�����ƃ}���[�����ő�K�̓v�����e�[�V�����͔|���n�܂����B�}���[�V�A�ł�1970�N�ォ��C�C���h�l�V�A�ł�1990�N�ォ��͔|���{�i�����C2006�N�ɂ̓C���h�l�V�A���}���[�V�A���Đ��E�ő�̐��Y���ƂȂ����B�C���h�l�V�A�̍�N�����_�̃A�u�����V�͔|�ʐς�1638��ha�i���{�̍��y�ʐς�43���j�ɒB���C�X�}�g�����ƃJ���}���^���i�{���l�I�j���ɏW������B�p�[������6���͑�K�̓v�����e�[�V�����C4���͏��_�̔_���Ő��Y����C800���l�ȏオ�p�[�����Y�Ƃɏ]������B�@
�@�C���h�l�V�A�̃p�[������7�����A�o�Ɍ������C�ő�̊O�݊l�����ƂȂ荑�ƌo�ς��x���Ă���B���E�̃p�[�����̎�v�A�����̓C���h�C�����C�p�L�X�^���C�o���O���f�V���ȂǓr�㍑����ʂ��߂�BEU�͐��E�̗A���ʂ�16���ŁC�o�C�I�R����53���C���d�E�M������12�����������邪�C2030�N�܂łɃp�[�����̎g�p�p�~�����߁C�C���h�l�V�A�Ƃ̊ԂŖf�Ր푈�������Ă���B���{�͐��E��1.4���ɓ�����70���g����A�����C80���ȏオ�X�i�b�N�َq�C�C���X�^���g�ˁC�A�C�X�N���[���C�}�[�K�����Ȃǂ��܂��܂ȐH�p�ŁC��l������N��5kg�ȏ������Ă���B�A�u�����V�͕c��A����3�N�ڂ�����n�\�ŁC�N�Ԃ�ʂ�2�T�Ԗ���20�N�]�������������B���̂��ߒP�ʖʐϓ�����̖��̐��Y�ʂ͑哤��10�{�C�i�^�l��6�{�ƗD�ʐ����ۗ��B
2�D�p�[�����Y�Ƃ̉ۑ�
�@�������A�u�����V�_����ۂɂ́C������̐X�т����̂���C�c��ȒY�f�������ł���D�Y���n���r�������B���������D�Y�n�ł͒n���Ђ��p�����_���Ƒ��܂��đ�ʂ�CO2��r�o���C���C�t�T�C�N���Ō���ƃp�[�����̉������ʃK�X�r�o�ʂ͉��ΔR����傫������C�C���h�l�V�A�̉������ʃK�X�r�o�ʁi�y�n���p�]�ω����܂ށj�͐��E��3�ʂƂȂ�B�A�u�����V�͔|�͔M�їт�D�Y�n�̔j��C�X�щЁC�쐶���������n�̔j���łȂ��C�n���R�~���j�e�B����̓y�n���D��J�����C�l���N�Q�Ȃǂ̖��������C�����p�[�����ƌĂꉢ�Đ�i���𒆐S�Ƀp�[�����ւ̔ᔻ�����܂��Ă���B
�@�p�[�����Y�Ƃ������\�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ�ڎw��2004�N��WWF�≢�B��Ƃ𒆐S�ɐݗ����ꂽRSPO�i�����\�ȃp�[�����̂��߂̉~���c�j�͍͔|���痬�ʂ܂Ō��i�Ȋ��ݒ肵�C��������_���ɑ��F���s���C�p�[�������i�̍��ʉ���}���Ă����B�v�����e�[�V������ƁC�H�i�≻�ϕi���H�ƎҁC�����Ƃ܂ŃT�v���C�`�F�[���S�́CNGO�C���Z�@�ւȂǑ��l��4812�̃X�e�[�N�z���_�[�������C���{��Ƃ�203�Ђ��Q�����Ă���i2020�N5�����j�B���E�ŗ��ʂ���p�[������19����RSPO�F�ؖ��ƂȂ����B
3�D�p�[�����Y�Ƃ̏����Ɍ����ā@
�@�C���h�l�V�A���{��2011�N�ȗ��D�Y�n�⌴���тł̃A�u�����V�J������������������C2018�N9���ɃW���R�哝�̂̓A�u�����V�E�v�����e�[�V�����̐V�K�J���i�v������\�������B��������N�̐��{�@�ւ̊č����ʂŃv�����e�[�V������8�����K���Ɉᔽ���Ă���ƌ��\�����ȂǁC�������ɋ^�₪�傫���C�K���̗l�X�Ȕ��������w�E����Ă���B
�@�V�K�J�����֎~����钆�C�p�[�������Y��4�����߂鏬�_�̓y�n���Y���͑�_����3����2�ȉ��Ɖ��P�̗]�n���傫���B���{�͐Ζ����A���̕��S�y���̂��߃p�[�����o�C�I�R������𐄐i���C���݂�B40 �̋`������ڎw���Ă��邪�ۑ肪�����B�܂��c��ȃo�C�I�}�X�����ł���A�u�����V�c�Ԃ��قƂ�ǖ����p�ŁC����H��Ŕ�������p�t�̃��^��������x��Ă���B�����������ŃA�u�����V�ʖ[�iFFB�CEFB�j�𗘗p�����n�敪�U�^�̓d�́E�R�������V�X�e��������Ӌ`�͑傫���B�@�@�@�@���@
2020�N6��25��
�p�[���_���̔_�Ǝ����̔R�����F �㗬���牺���܂ł̍��ۏ��i�V�X�e��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�R�E�T�|�[�g���ʌږ�i���s�喼�_�����j�@��W��O
�P�D���{�̖؎��o�C�I�}�X�����̌���@
�@�؎��o�C�I�}�X�͍Đ��\�Ȏ����ł���̂Ŏ����I�ɗ��p�\�ł���D�܂�؎��o�C�I�}�X�́u�����\�Ȕ��W�v�� �������邱�Ƃ��ł�����̂ł���B���{�ɂ����ẮC�؎��o�C�I�}�X�������G�l ���M�[�����ė��p���邱�Ƃ����߂���D�Ƃ��낪�C���{ �̖؎��o�C�I�}�X�����͕����ʂ�����I�ɏ��Ȃ��̂����� �ł���D���{�̏��Ȃ��؎��o�C�I�}�X �����̗��p�y�����邽�߂ɁC�����̖؎��o�C�I�}�X�����̗��p �Z�p���J������Ă���D�����ɂ��āC���Ȃ����{�̖؎�������L�����p���Ă����Z�p���o�C�I�}�X�����̕����� �������C�O�ŗL���Ɋ��p����`�����X�������Ă����D
�Q�D�C���h�l�V�A�̖c��Ȕ_�Ǝ����p�[����
�@�C���h�l�V�A�̃p�[���_���͐A�����ł���p�[��������v���i�Ƃ��Đ��Y���̌���ƍ͔|�ʐ� �̊g���i�߂Ă����D�C���h�l�V�A�ł̓p�[���_���̖ʐς͂��łɓ��{�̑S�k�n �ʐς�3�{�ȏ�ł���.
�R�D�C���h�l�V�A��2045�N�܂ł�GDP���E5�ʈȓ���ڎw��
�@2019 �N 10 ���ɃW���R�哝�̂͑� 2 ���̏A�C���Łu�C�� �h�l�V�A�� 2045 �N�� GDP ���E 5 �ʈȓ���ڎw���v���Ƃ� �錾�����D���݂� 5 �{�ȏ�� GDP ��B������̂́C���݂܂ł��܂�������Y�Ƃ̒��S�ł���p�[���Y�Ƃ̔��W�ȊO�ɍl�����Ȃ��D�p�[�������L���p������悤�ɂȂ����ő�̗��R�́C���i���������Ƃł���D�N�Ԃ�ʂ��Đ�ڂȂ����n�ł��邤���C�P�ʖʐϓ�����̐��Y���͐A�����̂Ȃ��ł����Ƃ������D
�S�D�R�����ւ̃p���_�C���]���͉��g����̊�{�헪
�@�A�u�����V����H�����ŗ��p������C�R�������邱�Ƃ̗D�ʐ��ւ̗������������i�݂���D�R�����ɕς��� CO2 �r�o�[���]���̃o�C�I�R���Ƃ��č����]���� ��C�����I�ɂ����|�I�ɕt�����l�����������\�ȍ��ۋ����͂������ėA�o�ɂ��O�݊l���ɂ��v���ł��邽�߁C�d�v�Ȑ헪�ɂȂ��Ă���D������ɁC�A�����Ƃ��Ẵp�[�����s��Ɍ��E�������o�����D�C���h�l�V�A�̃g�b�v�̓p�\��������R�����ւ̃p���_�C���]�������g����̊�{ �헪�A�o�ϔ��W�����͂Ƃ��Ĉʒu�t���Ă��邱�Ƃɋ^���� �]�n�͏��Ȃ��ƍl���Ă���D
�@
�T�D���{�E�C���h�l�V�A�Ƃ̑��ݘA�g���͂����R�̗���
�@�M�҂͍�N2���ɏ��߂ăC���h�l�V�A��K�₵�C���{�̎�g�݂ɐG��邱�� ���ł����D�����čł��p�[���_�������B���Ă��郊�A�E �B�y�іk�X�}�g���B�̍��c�̔_�ƌ��Ђ̃p�[���_�������@ ���邱�Ƃ��ł����D���܂ŁC���{�ł̓p�[���_���C�p�[�� �Y�Ƃ̂��Ƃ��w�ǒm���Ă��Ȃ��D�C���h�l�V�A�͗��j�I �ɂ��n���w�I�ɂ��ɂ߂ē��{�Ƃ̊W���[���D�ǂ������ ���ł���C�����I�ɂ��߂������݂ɘA�g���͂��邱�Ƃ����R�̗���ƎƂ߂Ă���D
�U�D�m�������Z�p�ł̔R�����V�X�e���̍\�z
�@�p�[���_���ł̃A�u�����V�̉ʎ��iFFB�j����A CO2 �r�o�[���]���̍Đ��G�l���M�[�Ƃ��Ă̔R�����ւ̃V�X�e���̓����́C�V���ȋZ�p�J����K�v�Ƃ��Ȃ��ŁC�V�X�e���\�z�ł��邱�Ƃł���B���Ȃ킿�C���Ɋ������Ď������Ă���Z�p�v�f�őg�ݗ��Ăł���V�X�e���������ɂ̖ڕW�ł���D��̓I�ɁC ���������R������������ S-GTCC�i���{�ł��̌��^������ ���Ă��鍂�����Ȕ��d�V�X�e���j�Ńp�[���_�����̃I���T�C�g�Ŕ��d����V�X�e������Ă���D
�V�D2050 �N�̓��{�ƃC���h�l�V�A�̃G�l���M�[�̎p
�@2050 �N�Ɍ������Ă̗����̃G�l���M�[�̎p�̏I���w��W�]�����DLNG �ƃo�C�I�}�X �R������ȃG�l���M�[�����Ƃ��Ċ��҂ł���D �����CLNG �ƃo�C�I�}�X�R���̗��p�Z�p�����ɏo���� ������, �m�������Z�p�̉�����ʼn��P�E���ǂ������Đi�� ���ĒB���ł��邱�Ƃ������D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@
2020�N6��20��
�C���h�l�V�A�̃p�[���Y�Ƃł̔R�����Ɋւ���V���|�W�E���i���ē��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ЃG�R�E�T�|�[�g�@
�@�����̓��m�Â���̃��b�J�A�N�ƉƐ��_����Ƃ̑傫�ȏW�ς�����܂��B2003�N�ɓ��{�Z�p�m��ߋE�{����Â̋Z�p�m�S�����ŁA�����̑����̊�Ƃ̂��x���āA���ʂ������܂����B6��26���i���j�ɃV���|�W�E�����J�Â��܂��B�z�[���y�[�W���g���Ė����V���ȏ�M�����ĎQ���҂����ɒB����܂ŕ�W���܂��B
�e�[�}�@�C���h�l�V�A�̖c��ȍĐ��G�l���M�[��������{�Ƌ����ŊJ�����p
�@�@�@�@2045�N�A2050�N�ȍ~�̃S�[���ւ̎����̃v���O����
�����@�@2020�N6��26���i���j13�F30�`16�F30
�ꏊ�@�@����㏤�H��c�����c���@�@��W���100��
��Îҁ@���G�R�E�T�|�[�g�i����㏤�H��c������A�����J���^�R���T���E�V���N�^���N�j
�X�P�W���[���@�@
13�F30�J��@��Î҈��A�F���G�R�E�T�|�[�g�������@�Z�p�m�@�������F�@
�@�@
�@�@�@�X�e�B�O���b�c�����i�m�[�x���o�ϊw��܁j�́u��������Љ�v�̎��H
�@�@�����A�@�C���h�l�V�A���̎���
�@�@�@�@�@�@�A���t�B���E�^�X���t�@�G�l���M�[�E�z��������b�̃��b�Z�[�W�̏Љ�
�@�@�@�@�@�@��b�͍�N10���܂ōݓ��{�C���h�l�V�A���a����g�B���{�Ƃ̘A�g����������
14�F00�`�@��u���@�@�@�p�[���Y�Ƃ̌���A�ۑ�Ə���
�@�_�O�i�ꎁ�@���O��E����ł̐l�ވ琬�ƁA�l���n���w�C�_���J���_�����n�Ŏ��H�B
�@�@�@�@�{���l�I���ł�30�N��50��̌���������ʂ��ăp�[���Y�Ƃ̉ۑ�Ɖ\�����Љ�B
�@�@�@�@�u�̉ԃv���������Ƃ݂̂��x����ɂ��Ĕ_�Ƃ̎��H�������B
�x�e
14�F45�`�@�@�p�l���X�g�̔��\�ƃp�l���f�B�X�J�b�V����
�@�@�@�@�@�@�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F�_�O�i�ꎁ�i�O�q�j
�@��W��O���@�@���s����w���_�����@�H�w���m�i�G�l���M�[�A�M�H�w�j
�@�@�@�@�p�[���_���̔_�Ǝ����̔R�����F�㗬���牺���܂ł̍��ۏ��i�V�X�e��
�@�@�@�@�C���h�l�V�A�͉��g�������i��2045�NGDP���E��5�ʂ�ڎw����g�݂̔w�i
�@�������F���i�O�q�j
�@�@�@�@�����^�Œn�敪�U�^�d�͐��������V�X�e���Ōo�ϓI�ŏ_��ȓd�̓l�b�g���[�N�\�z
�@�[�c�W�@�Z�p�m�i�q���H�w�j�Z�p�m��q���H�w����@�����s���q����u�t
�@�@�@�@��������S-GTCC�iSustainable Gas Turbine Combined Cycle�j���d�V�X�e��
�@�@�@�@���{�Ŏ��p�����ꂽ�V�X�e�����C���h�l�V�A��700�����̃p�[���_���ɕ��y������
�@�R�{�O�@
�@�@�@�@�K�X���^������̔R�ē����ƐV�^�R���i�E�B���X�̔����I�����Ƃ̗ގ����̈�l�@
�@�@�@�@40�N�ȏ�O�Ɏ��ؕ]�������R�ĉȊw�E���w�E�H�w�̎��_�ŏo���헪���l�@����B
16�F30�@��A
17�F00�`�@�@���e��i�ő�70���j�F���F2000�~�@�@�@
���Q���\���F�@HP�u�G�R�T�|�[�g�ʐM�v����Bhttps://www.eco-support.co.jp/
�@�@�@�ˁw�G�R�T�|�[�g�ʐM�x��HP�ɓ������獶���A�ڎ��́w�g�b�v�y�[�W�x���N���b�N�B
�@�@�@�@�V���|�W�E���ē��̍ʼn��i�ɉ��L�̈ē�,�ʐM�p�A�h���X�Ő\�����݉\�B
�@�@�@�@�Q����F2000�~�@�W�����{��A4��100�y�[�W�̕���X�����܂��B
�@�@�@�@�\���p���[���Ɏ���,���������L�����������B�Fdfaqv509@kcc.zaq.ne.jp
�@�@�@�@�����A�֘A���M���A����ɂȂ莟��A�\���E�L�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@��
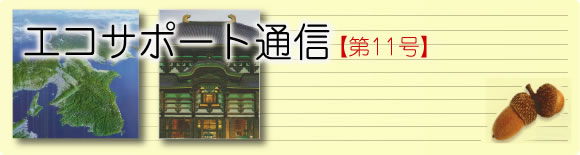
�͂��߂�
�V�R�K�X�ɂ�锭�d���Ƃ̎����́A�킪�������E�ɍv�����邽�߂ɕK�{�̎�i�ł���B�{�z�[���y�[�W��10�����y�ً}�z�u�G�l���M�[�헪�Ɠd�͂̈��苟���ɂǂ��������ׂ����v�i2012.5�D13�j�Ƃ��ĉ��L�̖ڎ��ɂ����J���Ă����5�N�ɂȂ�B
2013�N6���ɂ͋Z�p�m��ߋE�{����������i��\�����F�������F�Z�p�m�j�̊����Ƃ��āA�L���ҁA���Ƃ̋��͂Ĕ��d�̌v�搄�i�ψ���i�ψ����F��������喼�_�����j�ŁA�����ɑ��肤��V�R�K�X�ɂ���i�^�Η͔��d���iS-GTCC�j�����݂��ׂ��Ƃ������\�i���f�[�^�������N������j�āA���Ђ����Ƃ��p�������B���̌�̊�����ʂ���S-GTCC�����̂��߂̃V���N�^���N�Ƃ��ăv���[���[�E���Ǝ҂��x��������������m�ɂȂ��Ă����B
��������38���N�Ԑ��������Ă�����{�́u�܂��̕ω��ɋC�Â��A�ω�������A�������邱�Ɓv�ɂ��i�����Ă������Ƃɂ���B�l�Ԃ������̈�Ƃ��āA���̊��������ɏ]���K�v������B�������A21���I�̓O���[�o��������Љ�̒��ŁA��×����A���ƌ��͂��Љ�����傫�ȗ͂ƂȂ��āA���̌������傫���c��ł����B��ו�������A������Ă��܂��A�S�̂�����҂����Ȃ��Ȃ����B
�u�G�R�E�T�|�[�g�ʐM�v�Ƃ����v���b�g�t�H�[����2001�N2���ɑn�������B�o�ρA�Љ�A�Z�p�̓����Ȃǂ��L�������āA��M���Ă����B2011�N3���̕����������̂̌�A�����ɑ��肤����̂Ƃ��āA�n�[�h�A�\�t�g���ʂŎ��g�܂Ȃ��Ɛ��̒��͓����Ȃ����Ƃ��͂����肵���BS-GTCC�����Ɍ����ẴV���N�^���N�Ƃ��Ă̊����́A�����̗L���ҁE���Ƃ̂����͂Čp�����Ď��g��ł����̂ŁA�悤�₭��̓W�]�����������Ă����B
�u�G�R�T�|�[�g�ʐM�v�́A���̃V���N�^���N�Ƃ��Ă̖������ʂ������߂ɁA�p���I�ɏ�M����B���s�\���O���C�������肤�邪�A�N��4��A�l�G��Ƃ��ă��W�������f�ڂ���B3�����̊ԂɃR���e���c�������グ�Ďd�グ�邱�ƂŁA�p�����čŐV���M����d�g�݂Ƃ���B
�z�[���y�[�W�ł͍ŏ����̉���œ`���������Ƃ����������ƂɊȌ��Ɏ��������B�g�߂ȃG�l���M�[���̕������A���{�̃G�l���M�[�헪�������A�ǂ�ȍs�������ׂ����������A�ϊv�E�s�����N�������Ƃł���B���̂��߂Ɍo�ϐ��A�Љ�A�Z�p��Z�������`�Ń��X�N���ɗ͗}�����Z�p�V�X�e�������E�]�����Ȃ���O�i�E���������邱�ƂœW�]���J���Ă����B
���Ȃ݂���10���̃R���e���c�͈ȉ��̂Ƃ���ł���A�f�[�^�x�[�X�Ƃ��Ă͌��݂��L���ł���B
- �͂��߂Ɂi2012�N1���A���������̒܂ł̌o�܁j
- �G�l���M�[��{�v��Ɛ헪���ǂ��ǂނ�
- LNG(�t���V�R�K�X)�Ƃ�
- ���p�݂ɑ��ʂ�1000����W��LNG�Η͔��d���͂Ȃ��K�v��
- ���q�͂ƍĐ��\��ٷް(���z���A���͂Ȃ�)�Ƃ�
- LNG�Η͔��d���v��𐄐i���邽�߂ɉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���
�d�́E�G�l���M�[���Ƃ�܂��́A�t�ɂȂ��đ�����𐁂������悤�Ɋm���ɂڂ݂��c���ł����B2016�N�A�G�l���M�[�ǂݕ������G�{�u���z����̂�������́v�𐧍�E���s�����B�����{�z�[���y�[�W�Ō��J����ƂƂ��ɁA2019�N���܂łɒ����I�E�L��I�ɒʗp������{���̌����ɑ��锭�d�V�X�e���������ł��邩�A���̐헪�̓��m�ɂ��Ă����B
�M�҂̓K�X��ЂŌo����ς݁AS-GTCC�̌��^��1990�N��㔼�Ɋ����������B���{�̓s�s�K�X���Ƃ͂��ׂ�LNG�E�V�R�K�X�ɂ���Đ��藧���Ă���ŗD�ǂ̃v���[���[�ł���B
��11���̃e�[�} �u���{�̓s�s�K�X�̌o�����猩���鎝���\�ȃG�l���M�[�헪�v
�ڎ�
- �͂��߂�
- �����͂Ȃ��Ă�����Ă�����
20���I�̂Ȃ��A�ߋ��̃G�l���M�[ - �ΒY�Η͂̎O�̉ۑ�
- �n��̑�C������������L�Q����
NO�������łȂ������Ŗ���PM2.5�� - �n�����g���̎匴����CO2�r�o��
�V�R�K�X�Η͂�2�{�A���P�Ɍ��E - �o�ϐ��ł�LNG�E�V�F�[���K�X�ɏ��ĂȂ�
- �n��̑�C������������L�Q����
- �Đ��\�G�l���M�[�͑g�ݍ��킹��Η͔��d�d�͂��Ȃ��Ƌ@�\�ł��Ȃ�
S-GTCC�̑g�ݍ��킹�ɂ��n�Y�n���A�n�敪�U�^�̕��y�������ł���
- �����͂Ȃ��Ă�����Ă�����
- �K�E�I�m�ȏ�M�ŎЉ�̗����E������
- �G�l���M�[�ǂݕ������G�{�̐���E���s�@�i2016.5�j
- �_�_���i���Ĕ��\���ĕ]�����ꂽ�i2017.2�j
�u���{�̌o�����猩���鎝���\�ȃG�l���M�[�헪�v
�o�c���j
�@�@2019�N��5�ڂ�CO�Ƃ���Customer����Consumer�ɕύX�B�Ж��̃G�R(ECO)�AEcho(�G�R�[)�̂悤�ɐv���ɁA�I�m�ɃT�|�[�g���܂��B
| Economy | �o�� | Concept | �R���Z�v�g���� |
|---|---|---|---|
| Ecology | �� | Consulting | �R���T���e�B���O |
| Energy | �G�l���M�[ | Coordination | �R�[�f�B�l�[�g |
| Engineering | �G���W�j�A�����O | Communication | �R�~���j�P�[�V���� |
| Ethics | �ϗ� | Customer | �ڋq���� |
�Ɩ����e
�y�V�R�K�X�ɂ���i�^�Η͔��d�iS-GTCC�j�Ɋւ��R���T���E�V���N�^���N�z
�@���̃V���N�^���N�Ƃ��ăv���[���[�E���Ǝ҂��x�����܂��B
GTCC�F�K�X�^�[�r���R���o�C���h�T�C�N�����d�B�K�X�^�[�r���Ə��C�^�[�r���̃n�C�u���b�h�Ȕ��d�ō�������CO2�r�o�ʂ����Ȃ��V�X�e���ŁA1980�N��ɋZ�p�m�����A�L�����y���Ă���B
S-GTCC��S�̓T�X�e�C�i�u���A�����\������荂�����Ƃ������Ă��܂��B
