司馬遼太郎の「菜の花の沖」と高田屋嘉兵衛
この本は約20年前に書かれた。一作年、主人公の生誕地である淡路島で同窓会を開催し、現地の高田屋嘉兵衛記念館にも寄るべく、文庫本で6巻を読んだ。司馬遼太郎は嘉兵衛を極めて高く評価しており、その背景、要点をまとめた。
「人の偉さははかりにくいものですが、その尺度を英知と良心と勇気ということにしましょうか。では、江戸時代を通じてだれが一番偉かったでしょうか。学者、大名、発明家、いろいろいました。私は高田屋嘉兵衛だろうと思います。それも2番目が思いつかないくらい偉い人だと思っています。」 1985年洲本市での講演録より
- 生まれ・育ち(第1巻):淡路島西岸に水飲み百姓の長男として生まれた。
- 兵庫で船乗りに(第2巻):船乗りに、そして船主に。
- 辰悦丸と北前船(第3巻):28歳で北前船の辰悦丸を建造、北海道で「鮭、鰊、昆布」を仕入れ。
- 蝦夷の開発と嘉兵衛の仕事(第4巻):クナシリ島からエトロフ島への航路を開発。
- 蝦夷地の状況とロシア(第5巻):「沖の白帆は高田屋船」といわれ繁盛。ロシアと紛争が始まる。
- 嘉兵衛の抑留と帰還時の交渉(第6巻):1812年ロシアに抑留。その後帰国し国交正常化に貢献。
*1827年、嘉兵衛は淡路島で59歳でなくなり、その後、高田屋は松前藩の恨みを買い消滅した。
高田屋嘉兵衛の生き様や江戸時代の状況など
嘉兵衛は船乗りとして、事業家として 技術者としても優れていた
船乗りとして、天候を見、海岸を見、操船技術を磨くとともに、北前船による交易・航路を開発・拡大した。また、船の製作に当たっては、船大工と連携し、堅牢な船作りを進め、当時、嘉兵衛の店の船は一度も沈まず、当時としては稀有なことであった。
人間を大事にした
船乗りも最初は炊(かしい:飯炊き)から、経験を踏んでいくが、炊は周りから徹底的にいじめられた。また、蝦夷びとが松前藩から虐げられて、漁具もわたされない、食べ物となる植物の種や苗ももらえない状況に対し、 「みな、人ぞ!」として、人を大切にした。
人との出会いを大切にした
嘉兵衛は20歳で兵庫に出てきてから、28歳で最新鋭の辰悦丸を建造して北前船の航路を開拓、さらに、江戸幕府による蝦夷地の経営に協力しつつ、事業を拡大した。その間、多くの人との交流の中で成長していった。
さらにロシア船に捕まったが、ゴローニン少佐の救出、開放に当たっては、本人も抑留されたが、リコルド少佐との信頼関係をもとに、無事に交渉を纏め上げた。
江戸時代 ・保守政治と商品経済
江戸時代は徳川家康が、国内の武器を取り上げ、鎖国をし、基本的には農業中心の封建体制を確立した。そのため、何事においても、江戸初期の状態を保つ保守政治が行われた。例えば、鎖国政策の中で、船は帆が1枚に制限され、進展が妨げられた。
一方、江戸で使用する資材や物品は米や酒を始め、大坂から運び込むということで、商品経済が進んだ。北海道の鰊が肥料として棉の栽培が進み、人々の生活を豊かにするのに貢献した。
いじめ
日本では「いじめ」が伝統的に定着している。このようなことは、中国や海外ではみられない特徴といえる。例えば、淡路では村八分に合い、死の危険にもさらされた中で兵庫へ脱出した。
蝦夷地の経営
蝦夷地は米が取れないということで、松前藩に経営を任せていたが、ロシアの南下に備え、直轄地にするとともに、経済の自立を目指し手開発に取組んだが、官の経営は財政赤字を招くことにもなり、約20年で松前藩に返した。
日露関係の経過と現代
17世紀末からの膨張政策
ロシアでは17世紀末のピョートル大帝の時期から膨張が始まり、1世紀後のエカテリーナ2世の時期に進展した。シベリアもこの時期に毛皮の採取を目的に、地元の住民を支援する形で拡大した。18世紀末には、千島、サハリンにも進出した。日本からの食糧輸入などが求められた。
領土問題と交渉
- 1800年頃:ロシアが通商を求めてきた。鎖国政策の中で実現しなかったが、ロシアは蝦夷地(北海道)を視野に入れていた。交渉の結論は出にくく、ゴローニン事件は日本がだました形である。
- 1850年頃:ペリーの来航(1853)に伴い、1854年、日露和親条約が結ばれ、国境も確定した。
- 1900年頃:日露戦争の勝利により、千島、カラフトの国境が変わり、日本の領有が拡大した。
- 1945年:第2次世界大戦の敗北で、北方4島がロシアに占領された。
- 2000年頃:領土の返還問題を取り上げているが、未だに進展せず。それぞれに見方が違う。
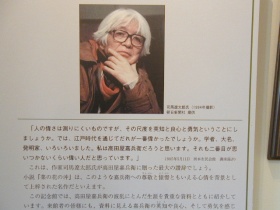 司馬遼太郎のコメント |
 北前船:辰悦丸の模型 |
 高田屋嘉兵衛 |
 高田屋嘉兵衛記念館(元の屋敷跡に) |