業務上でどのような本の作成に係わってきたか
文字を書くのが苦手だったのに、経験を積む中で共著などを含め形に残る冊子がいくつかある。作成に至った背景や、出版後の取扱について整理しておく。
1970年「ガス風呂技術マニュアル」(A4版130ページ)
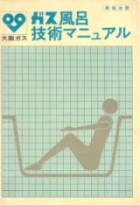
当時、ガス風呂の普及は、ガス会社にとって、収益の中心であり、高度経済成長の中で住宅の建設が続いていた。また、既築住宅においても内風呂の設置は必須になりつつあった。
1969年秋、ガス機器メーカへの出向から帰社し、風呂機器の技術担当となった。当時、大阪ガスの家庭用機器の販売チェーンは「サービスショップ」と「風呂ショップ」に別れており、支援体制が弱かった「風呂ショップ」に対する販売促進用ツールとして作成したものである。
過去のデータを整理し、電通の中村秀雄氏の全面的なサポートにより完成できた。当時は、天然ガス転換への準備作業が進みつつあり、風呂釜、風呂バーナーも板金や鋳物から量産型の仕様に変更されつつあり、浴槽も木製から、FRP(プラスチック)や鉄板プレスホーロー製に変換が進んだ時期でもある。
1983年「ガスニュース」別冊(A4版96ページ)

「ガスニュース」は大阪ガスがスポンサーの第3種郵便物として「建築にたずさわる方のために」というコンセプトで1963年に創刊した月刊誌である。
ガスの安全性対策や、エネルギー利用に伴う電気との競合が激化していた1980年に営業部に転勤した。住宅用ガス設備全般について、グループで隔月に特集記事を書き、これを別冊として取りまとめた。建築関係業界だけでなく、社内の開発部門や機器メーカーにも広く活用された。
しかしながら、残念ではあるが、2000年頃に「ガスニュース」は廃刊になった。
1984年「都市型集合住宅訪米実態調査団報告書」(A4版106P)

都市ガスの安全対策が国内で議論になっていた時期、早大講師兼現代計画研究所所長の藤本昌也先生を団長として11名で米国の集合住宅の実態調査団に参加した。
集合住宅の計画をどのように進めているかなど、建築設計に係わる方々の関心の一方で、都市ガスの安全性をどう考えて、建築に取り込んでいるかも大きな関心事であった。エネルギー事情は地域により異なるが、ニューヨークではマンハッタンにある超高層住宅の厨房設備として、都市ガスが広く使われていた。このことは、「ガスニュース」1984.10月号で「米国の住宅事情とエネルギー」として特集記事を掲載した。
また、調査団報告書は詳細情報として建築業界などに広くお届けした。この調査団はとてもメンバーの仲もよく、その後、私費でグループによるシンガポールやイタリアの住宅調査に参加した。現在でも忘年会時には、奥様方も参加されて東京で集まっている。
1995年「自動車排ガス問題の解決に向けて自動車NOx低減対策調査報告書」(A4版74P)

(社)大阪工業会(現在は大阪商工会議所に吸収合併)で環境問題推進委員会のもとに、大気環境問題などの対策について、産業界の立場でどのように行政施策に協力・貢献できるかを検討してきていた。
その中で、「都市域大気問題懇談会」を設置し、座長として主にディーゼル車の自動車NOx対策の現状とあり方について調査検討した結果をまとめた。
結論として、東京や大阪などの大都市域は産業や人口の集中度が高く、わが国固有の問題として取組む必要性があることを再認識した。
また、色々な施策があるものの、ディーゼル車の増加及び大型化傾向が続くことから、ディーゼル車の抜本的な排ガス低減対策が必須であることを確認した。
内容的には、マスコミや大阪府、大阪市など行政に大きなインパクトを与えなかったが、その後の推移を見ると、妥当な結論だったと考えられる。なお、このレポート発行の2年後にディーゼル車ではないが、トヨタからハイブリッド車「プリウス」が発売された。エネルギーは1/2、排ガスは従来の1/10と示されたが、排ガス1/10は、現在、大部分のガソリン車でこのレベルを達成している。
その後の共著による出版物
- 1999「ISO14001水質保全と排水処理対策」日刊工業出版社 (社)大阪工業会編
- 2005「実践現場の管理と改善講座 環境対策と管理」日本規格協会 名古屋QS研究会編
- 2007「工場長スキルアップノート」日刊工業新聞社 工場長スキルアップ研究会編
- 2008「現場リーダースキルアップノート」日刊工業新聞社 現場リーダースキルアップ研究会
いずれの本も、共著であり、品質管理、環境管理、エコアクション21、、マーケティングなどのコンセプト(考え方)などについて執筆担当した。