「課題先進国日本」―低炭素社会への取り組み― 20091210講演より
小宮山 宏氏 前東大総長、現三菱総研理事長
トヨタOB、三井住友火災海上保険㈱顧問兼自動車整備事業者団体ASKnet顧問
東京で開催された第11回目のエコプロダクツ展に合わせてシンポジウムがあり、小宮山宏氏が基調講演をされた。1000人近い会場であったが、超満員、キャンセル待ちの状態であった。
キャッチアップからフロントランナーへ
日本は欧米先進国のキャッチアップが続いたが、これからはフロントランナーとして活動していく必要がある。CO2の25%削減は日本のチャンスであり、無駄の排除、削減を進めることになるが、 個人の問題でもある。一方で高齢化の進展は早く、経済社会に大きな影響を与える。このような背景の中で、1999年にエンジニアとしてビジョン2050を提案した。その骨子は、次の3つである。
①エネルギー効率を3倍にあげる。②再生可能エネルギーを2倍に。③物質循環システムの構築
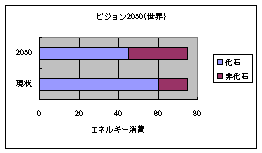 自動車は摩擦抵抗を除くと理論値(ゼロ)であり、エネルギーの1/10削減が可能である。今後、ハイブリッド車、電気自動車へと進んでいく。
自動車は摩擦抵抗を除くと理論値(ゼロ)であり、エネルギーの1/10削減が可能である。今後、ハイブリッド車、電気自動車へと進んでいく。
一方、セメントの生産プロセスは理論値に近づき、日本では第4世代のニューサスペンション方式になりほぼ限界である。今後はこの技術を世界に普及させていく必要がある。
日々のくらしでの省エネ化
CO2排出削減のためにライフスタイルの転換は良いが、管理、意識改革だけでは10〜20%の改善が限界であり、本質的な対策にならない。日本はものづくりで(世界を)リードしているので、今後は排出の55%を占める「日々のくらし」で削減する必要がある。
家庭部門では冷暖房用28%、給湯用30%、厨房用8%、動力用(冷蔵庫など)24%、照明10%のCO2排出構造であるが、今後は規制ではなく新しいやり方での取り組みが必要になる。
1kWの電気で理論値43kWのヒートポンプ冷暖房ができるので、COP3→6→12の改善が可能。また、住宅の断熱が30とするとエコハウスで100になるので、両方の組合せにより1/9にできる。具体的には、ヒートポンプ給湯、高断熱、エアコン新設、ハイブリッド自動車、太陽電池で1/5を実現できる。窓は2重ガラスなど。冷蔵庫買換えもあり、我が家では1990〜2001年は20000kwhだったが2008年〜は4000kwhと80%削減に成功した。
住宅の未来は燃料電池とヒートポンプで自動車並み産業になりうるのである。
また、東大では窓の内側に2枚目の窓を設置したが、これらの取り組みは省エネとともに生活の質が向上する。
言いかえれば、25%削減はすべきであり、日々のくらしで全体の11〜12%削減という試算をしたが、モデルでのシミュレーション結果と同等である。
冷蔵庫などは高効率製品に買い換えて、10年前後で回収可能であり、もったいないのはエネルギーである。これらをよく認識し、政策として自立国債(1〜15年)を発行し対策に適用するなど、国のほか自治体、企業でも初期投資を負担する仕組みをつくれば良い。
人口のピークアウトと高齢化
日本は2007年に人口がピークアウト(増加から減少へ)した。中国は2032年、インドは2040〜2050年にはピークアウトする。高齢化に向けては機能的な健康度を維持することが重要である。
今後は、新しい産業・新しい雇用・経済の活性化を図り、世界の先頭に立つ勇気を持とう。成長のモデルを途上国モデル(坂の上の雲)から、先進国モデルへと転換が必要であるが、そこは「霧の中」であり、課題に取り組み解決する必要がある。暮らしをよくしようと努力すれば、新産業が興る。
プラチナ構想ネットワークづくりの提案
自立分散型の地方と協調系の中央の協奏が必要になる。したがって全国各地に『魅力あるまち』づくりを進める構想が競争力の源泉となり、これを提案している。
わが国は、公害克服の経験がある。自らの課題解決を通じて人類をリードするのである。小さな国土、少ない資源、大きな人口、高齢化社会、産業先進国を目指すことが2050年の世界の姿に通じる。
コメント
東京まで講演を聴きに行ったが、十分に感銘を受けた。また、先生の講演にあった「地球持続の技術」岩波新書1999年発行と『「課題先進国」日本』中央公論新社2007年発行を早速購入して読み、ご講演の内容を再確認した。
前者は人類と地球の持続可能な発展を可能とする具体像を科学と技術の観点から2050年ビジョンとして提案したものである。後者はフロントランナー、先進国としての自覚を持ち、「本質を捉える知」「他者を感じる力」「先頭に立つ勇気」の獲得を求めている。必要なビジョンが多岐にわたる中で「他者を感じる力」など三つを身につけ進むことが重要と示している。