共著による出版物の製作(その2)
1)1999「ISO14001水質保全と排水処理対策」日刊工業出版社 (社)大阪工業会編
経済団体である大阪工業会(現大阪商工会議所と合併)は環境問題及びものづくりを中心とする産業界での問題の取り組みに歴史と特徴のある団体である。会社で環境部に異動になった1989年以来、環境推進委員会の大気・水質分科会などでお世話役することになった。
大阪府の環境行政におられた方が、1960年代からの環境問題に関する知見を出版物にまとめたいとの要望を持ってこられた。産業界では、公害対策として排水処理対策が最も広く共通的なテーマとして関心があり、活性汚泥法による生物処理などが広く普及していた。この処理方法は家庭用の浄化槽にも使われているポピュラーな方法であるが、企業の環境担当者だけでは現場の個別の状況は把握できても体系的な整理と対策方向を示すことは難しい。
そこで、技術士会の専門家の方々に執筆に参画して頂き、産業界担当者との共同作業として本冊子を取りまとめた。私は全体の調整役という役回りである。最新技術を持っている企業に紹介記事を書いてもらい、冊子の販売にも協力いただくなどの試みも実現させた。ISO14001は環境負荷の低減に向けた取り組みであり、参考図書としての利用が期待された。
引き続き大気編を書く計画もあったが、長い間活動してきたが異動のため、担当できなかった。また、ISO14001の活用については設備投資を伴う改善などに対するニーズはそれほど大きくなかったが、先進的な出版物だったし、多くの新しい経験ができとこともあり、製作のプロセスも楽しめた。
2)2005「実践現場の管理と改善講座 環境対策と管理」日本規格協会 名古屋QS研究会編
名古屋QS研究会というグループがある。日本規格協会が生産管理全般に係るテーマでの企業向けのシリーズ本を出版している。この推進役が同会であり、日本生産管理学会の副会長である澤田善次郎先生(椙山学園大学教授、技術士、中小企業診断士)のリーダーシップの元に企画を実現させてきた。
この中で、安全管理、原価管理などの冊子を化学企業である㈱カネカOBグループが執筆を担当したが、引き続き環境管理について取組むことになり、執筆メンバーに加えてもらった。
執筆するに際し、内容をどのように構成し、どの程度のボリュームにするか、誰が執筆を担当するかなど、集まるたびに議論し、会議の後飲みながら大いに放談した。執筆作業はなかなか進まなかったが、楽しみながら何とか完成した。生産現場における環境管理を進めるための実践的な内容がどの程度身近なものになったかは定かでないが、執筆者としてはそれなりに充実感がある。
最終章で今後の環境問題を考えるための世の中の変化と対応の方向性について以下のように取り纏めたが、現在の社会で起きている事象は、これらの変化に根ざしているといえる。
①地球環境問題
例えば自動車について、エネルギーと資源、環境問題には限界と大きな変革が必要である。とくに地球温暖化防止への対応が21世紀の最大の課題である。問題解決に向けては、目標を決め政策を展開する必要がある。わが国が民社党政権になり、国連の気候変動問題のサミット(2009年9月)で鳩山首相が「わが国は2010年までに温室効果ガスを2020年までに25%削減する」と発表し、国際的なリーダーシップをとるようになることは、到底予想できなかった。
②グローバル化、情報化
世界の経済活動が大きく、広く、早くなるとともに、企業の影響力が増大し、一方で社会的な責任を果たす必要性(CSR、SR)が増大する。企業はリスク対策に対して準備する必要がある。有害化学物質対策としてEUがRoHS指令を発効させ、さらに引き続いての対応が望まれている。
③ (わが国の) 少子・高齢化
成熟化社会への変化とともに、人間、生活などに重点を置いた生き方が重視されるようになる。 一方で女性の社会進出などが必須になってくる。
この問題の深刻さと
④(問題意識などの)共有化・協働化
情報公開、共有化が基本となってくる。これを前提にして社会の変化に向けて協働作業が進むとともに、企業は社会の信頼を獲得することが求められる社会になる。
3)2007「工場長スキルアップノート」日刊工業新聞社 工場長スキルアップ研究会編
日刊工業新聞社の「工場管理」という月刊誌に上記のグループで連載の記事を書いていた。これをさらに肉付けしたのが「工場長スキルアップノート」である。40テーマを抽出し、それぞれ図表や解説記事を入れて各4ページで構成するもので、2007年の「工場管理」臨時増刊号として発行し、その後、単行本として再発行された。私は工場勤務経験が少ないので、工場長として知って欲しいマーケティングや品質管理の応用などについての記事作成を担当した。
この冊子は内容的には充実しているが、読み物としてはやや重いものになった。
4)2008「現場リーダースキルアップノート」日刊工業新聞社 現場リーダースキルアップ研究会編
「工場長スキルアップノート」の経験に基づき、現場リーダーの方々に役に立つ本を作ることになった。リーダーの島雄さんが、澤田先生や編集者と相談してテーマを80とりあげ、各2ページでイラストや図表を半分入れ、いつでも見出しを見て読みやすいように工夫して進めることとなった。
方針・骨格が決まると作業は進めやすい。「ヒトづくり」「モノづくり」「組織づくり」に加えて「ユトリづくり」の4部構成とした。それぞれのテーマに少しずつ参画したが、「ユトリづくり」については私がリーダーとして内容をまとめた。ユトリづくりは余裕のない厳しい現場で受入れられるように工夫が必要である。そこで、経営者が従業員の生きがいのある職場作りを意識しだしたという設定で、現場と遊離しないように注意しながらテーマを肉付けした。
①製造現場のユトリとは、 ②ユトリは心の持ちよう、 ③備えあればユトリあり、 ④ムダ取りで時間のユトリを生み出す ⑤書類のムダ、会議のムダをなくしてユトリをつくる、 ⑥創意を活かせばユトリは生まれる ⑦指示待ちをやめればユトリは生まれる
生産性優先でなく作業者の心の余裕を生み出す自主的な取り組みの重要性を意識したものとして解説した。
この冊子は「工場管理」の2008年臨時増刊号として発行され、その後、すぐに単行本になり、刷り増しも行われた。製作を担当したメンバーの満足度も高く、大阪で出版記念パーティーを行い、澤田先生を始め多くの方が出席してくださった。思い出に残る出版物の一つである。
5)2008 「ISOマネジメント」特集記事 日刊工業新聞社
2008年12月号で「エコアクション21マネジメントシステムの活用」について54ページの特集記事として詳細を紹介した。私が取り纏めを行い9名で執筆したが、詳細は省略する。
 |
 |
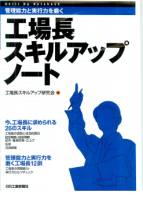 |
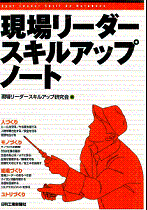 |
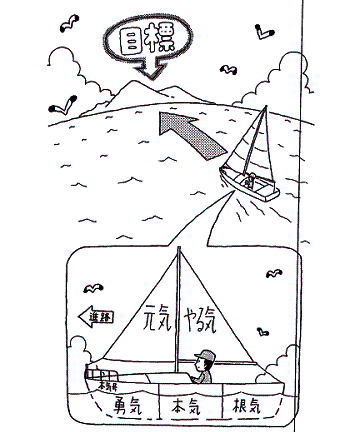 |
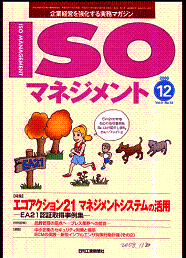 |
||