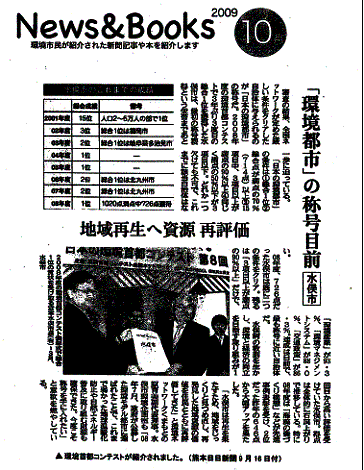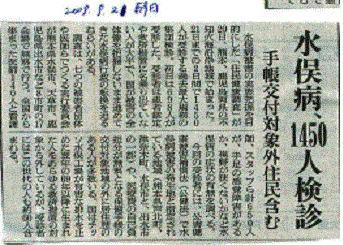環境モデル都市(北九州、水俣)、環境首都を訪ねて (08年9月、10月)
日本政府が低炭素社会づくりに向けて、2008年7月に北九州市や水俣市(熊本県)など6都市を選定。また、2009年1月に京都市など7都市を追加して環境モデル都市として選定した。
一方、NGO団体11で構成し、京都にある「環境市民」が主幹事として毎年「環境首都コンテスト」を実施しているが、両市はこの数年は常に1位、2位を占めている。
2008年の秋に北九州市と水俣市の現地を訪問する機会があったので現地を見た感想を述べる。
北九州市の環境への取り組み
技術士会近畿支部環境研究会の一泊2日の研修旅行として12名で訪問した。期待通りの視察ができ、とても有意義であった。詳細は、環境研究会で発表したし、[Technology]というホームページ(「PE-eco」に改称し再編する予定)に参加者の感想を紹介している。
下表は環境首都コンテストで15項目について評価し(2006年)、北九州市が7項目で最高得点をとったことを示している。私たちはまず、全国で最初にできたエコタウンとこれを実現してきた産業政策の先進的な取組みの実情について市担当者から説明を受けた。その後、現地の施設見学をした。全国で最も早く高濃度PCBの処理施設が立ち上がったが、情報公開が進み、住民との信頼関係を構築しつつ、長期的な視点の中でエコタウンでの事業が定着しつつある状況を目の当たりに見られた。
市庁舎などに「環境モデル都市」になったことの表示が随所に見られ、活動が定着しているとともに、適切に市民にPRできていることを実感できた。
また、市民の意識向上を目指して、市担当者から直接説明と質疑をさせて頂いた。その後、エコタウン内の「エコタウンセンター」で小学校4~5年生向けに環境教育・研修の場として受入れて活動している。VTRでの概要紹介、環境問題について分かりやすい展示の工夫と説明があり、見学を通じて楽しむことができた。
同市は高度成長期の産業公害を経験し克服して来た歴史がある。現在はこの経験を活かして地域の活性化を図り、実績を積み上げている姿に接することができ、参加者一同深い感銘を受けた。
| 項目(2006年度の高得点自治体) | 自治体名 | 得点 | 配点 | 得点率 (%) |
| A ローカルアジェンダ21・環境基本計画等 | 日進市 | 66 | 95 | 69.5 |
| B 環境マネジメントシステム | 水俣市 | 47 | 50 | 94 |
| C 住民とともにチェックする仕組み・情報公開 | 北九州市 | 42 | 50 | 84 |
| D 自治体内部における環境基本行動 | 宇部市 | 47 | 55 | 85.5 |
| E 自治体との交流 | 北九州市 | 34 | 40 | 85 |
| F 職員の資質・能力向上と環境行政の総合化等 | 北九州市 | 57 | 90 | 63.4 |
| G 住民のエンパワーメントとパートナーシップ | 大和市 | 75 | 85 | 88.3 |
| H 環境・まちづくり学習 | 北九州市 | 71 | 80 | 88.8 |
| I 自然環境の保全と回復 | 水俣市 | 70 | 70 | 100 |
| J 健全な水循環 | 松山市 | 36 | 40 | 90 |
| K 風土を活かした景観形成と公園づくり | 尼崎市・多治見市 | 41 | 50 | 82 |
| L まちづくりと一体化した交通政策 | 北九州市 | 56 | 65 | 86.2 |
| M 地球温暖化防止・エネルギー政策 | 北九州市 | 56 | 80 | 70 |
| N ごみの減量化 | 北九州市 | 46 | 60 | 76.7 |
| O 環境に配慮した産業の推進 | 水俣市 | 54 | 60 | 90 |
水俣市を訪ねて
私のホームページ「エコサポート通信」で、水俣病に関連して3回取上げた。
第3号(2001.4):「水俣病と技術倫理」小林廣氏(立命館大学非常勤講師)などの報告書より
第6号(2005.2):「水俣病の(最高裁)判決を考える」小林廣氏の寄稿
第7号(2008.9):「水俣のもやい直し」日経ビジネス特集号2007.4.30からの要約
一度現地を訪れたいと考えていたが、熊本での会合に参加する機会があり現地調査を実現できた。
熊本空港を降り立ってすぐにレンタカーで約100km南へ下る。途中までは高速道路が整備されているので、2時間足らずで水俣へ到着した。県の南端、鹿児島県に隣接する、海と山に囲まれた小都市である。
昼前に到着したので、郊外の海沿いの「湯の児温泉」で温泉につかり、ゆったりとした気分になった。ここで市内の様子を確認し、まず、水俣市役所を見学した。
水俣市は水俣病を経験したことから、環境問題には熱心に取り組み、1999年に自治体としては全国で6番目にISO14001を認証取得し、その後自己宣言により活動を継続している。また、環境モデル都市としての取り組みを1992年に宣言し、推進してきた結果、環境首都コンテストに応募し、常に上位にランクされている。また、2008年7月には全国で6都市が認定された「環境モデル都市」にも選ばれて、これに関する大きな表示を掲示して市民にアピールしている。
また、リサイクル等の積極的な取り組みを進めるため、ゴミは22種類に分別するとともに、全国で13番目のエコタウン事業が認められ、7つの施設・工場が稼動している。
市役所のロビーに面した環境へのPRコーナーでは、「チッソ」の液晶部品など10以上の主力製品群についての掲示が印象的であった。
次に市域の南端にある3つの展示施設を見学した。
水俣湾にある海底の汚染物質を浚渫し、この土砂を埋立てて広大な土地を造成し、跡地をエコパーク、公園等として活用している。埋め立て後1997年には海の安全宣言をして、漁業が復活し、さんご礁の定着など、海の汚染が解決したことが伺える。この埋立地に隣接した高台に3つの施設が設置され、多くの見学者を受け入れている。秋の行楽時期でもあり駐車スペースには観光バスが多く来ており、小学生を中心に社会見学のメッカとして賑わっていることが印象深かった。
①水俣市立水俣病資料館
最初に15分ほどのVTRで水俣病の発生から対策にいたった経過が映像や新聞記事等で要領よくまとめられている。この後、館内の展示室で悲惨な水俣病の発生と闘争、現在に至るまでの状況が見学できるので、小学生や市民にとっても分かりやすい展示館となっている。
②水俣病情報センター(国立の施設)
水俣秒に関する国立水俣病研究センターの関連施設として、資料、情報の収集・管理と展示がされるとともに、水俣病健康相談室が設置され、現在でも患者さんに対する支援が続いている。
③熊本県環境センター
これからの環境を考え、実践するための施設で、ゴミのリサイクルなどを学習することができる。
多くの小学生が学習の一環として参加されていた。また、環境センターだより「エコタイムズ」を年に4回発行して、環境啓発活動の概要を紹介している。
これらの3つの施設が存在することで、環境学習の場として有効に活用されている。ここは八代湾や天草などの島々が一望でき、自然環境の保全を含め、目で見、肌で感じられるような場となっている。ちなみに来館者は現在までに61万人の表示がされていた。
施設見学の帰り道、水俣駅の正面にあるチッソ水俣本部の向上の表玄関がある。さらに国道を北上すると、市域から少し外れた場所に九州新幹線の新水俣駅がある。新幹線は北へ40kmほど離れた八代駅まで通っており、熊本へ帰ると駅の周辺に博多までの九州新幹線の建設工事が進んでいることが実感できた。
しかしながら、南国の明るい日差しの中で、水俣病は過去のものとなりつつあるが、水俣病に関する検診の知らせや健康相談などがまだ続いていることを見ると、まだまだこの問題が広域化しつつ、終わっていないことを痛感させられた。水俣市の環境問題に対する取り組みの一方で、厳しい現実を考えさせられる一日であった。