技術士全国大会(仙台)に参加して(09年10月)
技術士全国大会に参加したのは6年ぶり3回目である。仙台まで足を運んだ甲斐があり、よい刺激を受けるとともに、技術士としてのあり方を考えるきっかけにもなった。
1. 西澤潤一先生の基調講演「将来社会の見通しと科学技術の役割」
西澤先生は82歳、文化勲章を受け、ノーベル賞候補にも擬せられている技術者の代表となる方であり、東北大学総長も勤められた重鎮として今も活躍されている。
技術は金儲けの手段として考えられる宿命にあったが、中長期的な戦略を考え、展開していく上で役割が増大しているとの経験に基づく講演は説得力があった。
①人間はどの程度エネルギーを使うか
初期の農業から脱穀用の水車、さらに風車の利用を経てスコットランドで序危機感が普及し、グラスゴーは造船業で大きく飛躍した。また、自動車は欧州ではなく米国で発展し、エネルギーの一人当たり消費量は20世紀に急増したが、無駄も多い。
一方、人口の増加はエネルギーと相関が大きい。電気の利用により夜が明るくなり、暖房ができ、移動、医療も進み、人口増もありエネルギー使用量は急増した。
②CO2放出量と大気中CO2濃度の予測
南極の氷にはCO2が入っており、南極の研究者がお土産にした氷を分析すると18世紀からのCO2の増加が確認できる。これを東北大総長の時に計算して対数グラフにしたところ、直線的に増加することが確認できた。このままでいくとCO2の増加により、2200年にはCO2の増大で人類は滅亡する恐れがあるとOPECの総会時に説明した。
③交流か直流か
交流は変圧できるから、広く使われているが、長距離に大量の電力を輸送する場合は直流送電の方がロスが小さい。中国の三峡ダムから上海への電力輸送はスエーデンの会社が直流送電で受注した。わが国では関西電力が瀬戸内海(徳島から和歌山)へ直流の海底送電線を敷設した。将来は高圧直流送電ネットワークが有望である。また、周波数をあげると設備の規模は非常に小さくなるので、衛星やロケットで使用され、新しい技術システムの可能性が開ける。例えば光ファイバーの開発により、世界中に2万kmのループができる。
④只見川の最新の発電所のシステム
水利権は農民にある。使い捨てしないで権利を貸してもらうことは可能であり、多数のダムを作って渇水期に有効利用したり、エネルギー貯蔵もできる。
このように、科学技術者には大事な仕事が多くあるし、活躍の場も沢山ある。
Q&A
Q:CO2の削減問題について
→1976年に問題提起した。レイチェル・カーソン(米)は科学について警鐘を鳴らしたが、CO2については触れていない。CO2は**%削減といって、早くスタートさせるべきである。
Q:ダイオードについて
→ポンコ氏(ロシア→米)の発明で、ガリウムと砒素を入れたものをスタンレー電気で開発し、米国で発光ダイオードを売り込んだ。評価が高かったが、日本では車のライトから逆輸入された。信号機も反射しないので分かりやすいが、日本の警察で採用されるまでに時間がかかった。
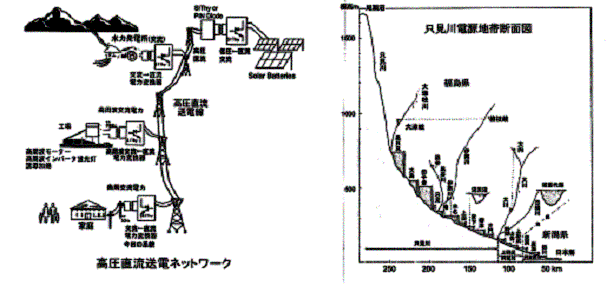
2. 全国大会でのディスカッション
次の5つの分科会と前日に行われた技術者倫理の分科会があった。
①食の安定的な確保と安全な供給
②資源・エネルギーの有効利用と循環型社会
③地震災害に備え、地域社会の安全向上に貢献する
④技術のマネジメント
⑤中立公正の堅持と自立的な規範
次の3分科会を傍聴した。その議論から印象的ものについて述べる。今回は東北支部、仙台での大会であるが、実行委員会では全国から情報を収集し、幅広い意見発表とディスカッションがあった。
a)技術者倫理を考える
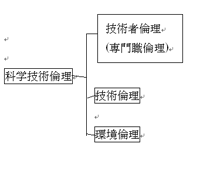
科学技術倫理の体系化に向けた教育の実践例ということで発表された鳥羽瀬孝臣氏の発表が印象に残った。自身で勉強して千葉大学などで講師として科学技術倫理を3つの視点で整理して、実践している内容の紹介である。
15の講義の内、環境倫理(生物多様性)、環境問題(地球温暖化)、リスク・コミュニケーション、合意形成などのテーマと、土壌汚染、水俣病、温暖化政策等の事例研究を踏まえたカリキュラムの概要が紹介された。この内容を踏まえて、大阪で講演を聞く場を設定し、了承された。
他に中部支部では、技術倫理についての勉強会を継続しているとのことで、「作動中の科学」として未知な領域を含みながら、これを既知とする努力が続けられているとの発表などもあり、
原子力問題などをどう捉えるかと問題提起したら、発表者から活発なコメントがあった。技術士の専門分野に原子力・放射線部門ができたが、原子力に携わる方からは、翌日の資源・エネルギーに関する分科会で、原子力の出番が回ってきたとの認識が示された。
b)「技術のマネジメント」
パネリストの発表が終わったあとのディスカッションから参加した。失敗経験を蓄積して生かす仕組みづくりが必要との意見の中で、三菱重工グループの方が、ISO9001を構築しPDCAをまわす取り組みが有効と考えて、現在、システムを構築して、技術の伝承に役立てたいとの発言があった。たまたま、私は昨年、日本生産管理学会で同様の発表をしたので、同様の思いを強くした。
一方、理学部出身で情報誌を作り、地域で発信している方(技術士ではない)から、技術士のことを知らなかったし、社会に知られていないことが指摘された。人は取り組みのプロセスを理解してもらいたいという自然な気持ちがあるが、内輪のナルシズムやストイシズムであってはならない。社会の変化の中で技術士の姿が見えてこない、もっと外部に発信する努力が必要との指摘があった。このような見方があるということを深く受け止める必要があると思う。