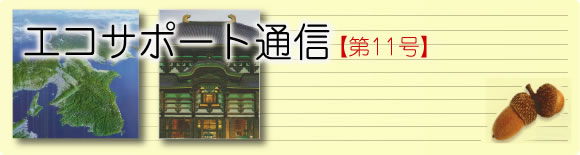
はじめに
1. 原発はなくてもやっていける
a)福島の復興と原発再稼働への動きは、遅々としている。原発なしでも電力供給はできている、やっていける、長い目で見れば原発はない方がよいという意識が広く定着してきた。
b)原発の新設・増設について住民合意をとることは不可能といえる。安全対策費用が大きく膨らんで、経済的にも新設のメリットはない。2011年に福島原発が発生した時、ドイツは従来の方向を変更して2022年に原発全廃、これを太陽光、風力など再生可能エネルギーで代替する戦略をとった。この戦略を日本に適用することは難しい。
c)台湾のエネルギー事情は日本と類似している。台湾は原発廃止の法律を制定し、2025年までに太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーで代替する戦略をとった。ただし、再生可能エネルギーを有効に活かすため出力を調整できるLNG・天然ガスによる先進型火力発電(S-GTCC)との組み合わせが必須であり、日本の経験を活かすことでより強力で有効なシステムになりうる。
2. 石炭火力は存在間が薄くなってきた
石炭は豊富な資源であり安価に供給(調達)可能であるとして、経済性が高い発電システムと位置づけられてきた。11.25万kw以上の火力発電所は環境影響評価の対象であり、地球温暖化対策の観点から、CO2排出原単位が多い(下記b)参照)。40年間も稼働させることを考えると計画を避けるべきとの厳しい意見が多く、計画が進まない。
11万kW規模の石炭火力は20年以上の設置実績があり、収益性の高い事業と位置づけられている。発電事業者は燃料調達や運転管理状況が把握できると、事業のひな型をもとに利益を生む事業として銀行などの金融機関から事業資金の融資を受けることができる。信用力のあるエネルギー事業者や商社の参画を得て発電事業計画を他の地域でも水平展開して事業化が進んでいく。 ※仙台市では石炭火力の新設については規模に関わらず、すべて環境影響評価条例の対象とした。
実質的に 計画が認められなくなった。(2017.5施行)
石炭火力の三つの課題
a)地域の大気環境を汚染する有害物質
中国ではPM2.5によるスモッグの深刻な公害被害を発生している。仙台市では条例により大気汚染のリスクはがある小規模な石炭火力発電(3万kW以上)の設置を実質禁止した。すでに計画が進んでいる11万kW(国の環境影響評価法の適用規模以下)の計画は、事業者が権利を主張して強硬建設すると、数年後には負の遺産として事業者は不合格点のレッテルが張られる。
おそらく事業者は撤退の道を選ぶことになる。3万kW以下の規模については、設備費、運転費が相対的に割高であり、経済性・事業性が低く普及は進みにくい。
b)地球温暖化の主原因のCO2排出量
石炭を燃焼させると大量のCO2を排出する。天然ガスは水素分が多く燃焼させやすいが、同じ電力を発生させるのにCO2を2倍排出する。技術開発を進めても少し良くなる程度で、根本的な解決にはつながらない。(先の展望が低い)
c)経済性でも石炭火力はLNGに勝てなくなった
2000年代に始まった米国のLNG・シェール革命で米国は、中東から輸入していた石油を自国で生産対応できるようになった。この影響で、2015年から石油価格は従来の半分以下に下がった。LNG・シェールガスは膨大な埋蔵量があることが確認された。また、LNGはオーストラリアや中東のカタール、ロシアなどで大量に生産が拡大しており、これに加えて世界中に広く埋蔵されているシェールガスが加わるので、今後100年以上にわたり安定した価格で調達が可能なシェール革命が続く。
石炭火力は1980年頃、米国内で発電電力量の過半を占めていたが、現在は天然ガス火力への置き換えが進み、30%程度までに減少した。トランプ大統領は石炭産業を衰退から守るべく、普及策を取りつつあるが、経済性で競争力を失ったので、シェアの減少が緩やかになる程度である。
石炭火力は燃料中の灰の処理や排ガス中の大気汚染物質の処理が必要である。ボイラーの運転・維持管理も複雑で、3万kW規模では割高になり、経済性が出にくい。LNG・天然ガス火力の設備費は、概ね石炭火力の1/2以下で、長期間、性能安定維持管理もしやすい。国内でも、すでに石炭離れが始まっている。
3. 再生可能エネルギーは組み合わせる火力発電電力がないと機能できない
a)わが国の電力網はEUと異なる
ドイツでは再生可能エネルギーで原発の代替戦略を進めているから、日本でも同様の戦略で対応できると広く信じられている。ドイツを中心にEUでは地域全体の電力網が細かく張り巡らされて、インターネット推進網のように国を超えて供給することができる。それでも多くの課題が顕われている。
わが国が戦後作り上げてきた9電力体制ではそれぞれの電力会社内で独立して電力を作り供給するシステムである。わが国は70%が山岳地であり、平地では高密度の経済活動が続いている。送電網の建設コストが高く、欧米のようなメッシュ型にはなっていない。都市ガスはパイプラインで供給するのが最も効率的であるが、都市ガス供給地域は国土面積の6%である。建設コストが高く、経済的でないことを示している。
我が国は2012年に「再生可能エネルギー特別措置法(FIT法)」が成立、施行された。太陽光発電の電気を20年間高価格で買い取り保証する制度である。家庭の屋根面ではなく、収益性が高い事業として大規模なメガソーラーが急激に設置普及した。しかし、2017年に同法が改正され、たので、事業者にとってのメリットはかなり制約を受けることになった。
例えば九州は太陽光発電が急激に増加したし、高圧送電網で関西や中部地区に送電が可能である。しかし、九州電力地域内で発電電力許容量をオーバーする場合、電力会社は地域内の電力安定供給に支障をきたすので、受け入れを制限する。余った電力を関西に送る前に供給制限・遮断せざるを得ない。再生可能エネルギーを優先使用したいが、システムが制御できなくなるからである。また、関西や中部などの大都市域ではエネルギー消費量が膨大であり、九州から送られてくると仮定しても電力需要のごく一部しか賄えない。首都圏は西日本の60Hzではなく50Hzであり、再生可能エネルギーの供給は北海道や東北地方からになるが、九州と同様の事態になる。電力は貯めることが難しいから、経済性とバランスのとれた発電システムの構築が必須になる。
日本ではマスメディアや学識者の声が反映されやすく、行き過ぎた制度設計を事前ではなく事後に手直しする例がよくあるが、再生可能エネルギー政策は典型的な例の一つであり、今後も国民負担の大きさなどの問題が顕在化する可能性が高い。
b)太陽光発電と組み合わせる地産地消、地域分散型システム
火力発電は大規模なほど発電効率が高く、発電コストが低い。しかし、50万kW級の火力発電は環境影響評価の手続きについて、事業者は住民合意を得るための経験が少なく、着工までのリードタイムが長いなどリスクが大きい。
小規模なコージェネレーションは現場で熱と電気を同時に利用できるので、再生可能エネルギーと同様に新電力として取り扱われるなど地方自治体などの期待が大きい。例えば静岡県や浜松市は太陽光などとともに「新エネルギー等倍増計画」を強力に推進している。
『LNGによる先進型火力発電(S-GTCC)』の『LNGによる先進型火力発電(S-GTCC)』で詳細に述べるが、従来の概念でコージェネレーションとして普及させるには限界がある。コージェネレーションではなく発生した蒸気からもタービンを回して発電する発電専用のS-GTCCは地産地消、地域分散型として優位性を発揮できる。
- 既存の送電網や、ガス導管を利用する
- 太陽光など出力が不安定な電源との組み合わせで、地域の電力の安定供給に寄与できる。
- この場合、太陽光などでできた電力は、FITの制度の考え方から、発電価格はゼロ、CO2排出量もゼロカウントになる。したがって、地域のガス事業者や新電力会社が取り扱いする場合、身の丈に合った規模で大規模火力と同等のパフォーマンスとして扱われる。メリットオーダーという考え方であり、長期間稼働しても優位性が確保できる。
c) 化石燃料から脱却する道筋はLNG・天然ガスへの切り替えから
小泉純一郎元首相は、原発のないエネルギーシステムへの脱却を強力に推進している。しかしながら、原発に代わりうるものは再生可能エネルギーであると主張して具体策がでてこない。一方、経済界は、安い原発の電気を待望しており、政府も原発の再稼働に期待している。
問題は、新設・増設は日本ではもちろん、海外でも極めてリスクが大きいことである。米国では、30年間原発の新設がなかった。東芝と子会社のウェスティングハウス社が2基受注したが、安全対策面の強化、設計変更を求められて、1兆円規模の赤字を発生させて、なお稼働までの道筋が見えない。英国では日立が千億円弱近くで原発受注に向けて取り組んでいる。英国でも過去20年間原発の新設実績がないことから、リスクは極めて大きい。
2050年を想定した場合、わが国でも原発は実質的にゼロになっている。化石燃料はCO2を排出するから再生可能エネルギーであるべきとの神話・信仰・願望に頼るわけにはいかない。
2050年には地球温暖化のリスクから解放されるために、わが国はCO2を80%削減させるべきとの議論が大きな影響力を持っている。
わが家のエネルギー利用を例に考える。30年前に家を建て替えた。(1)熱利用は都市ガス、(2)電力利用、(3)自動車用、(4)食料としてのエネルギーの利用設備も利用形態は30年間ほとんど変わっていない。つまり30年前と現在とは、エネルギー消費構成と消費量は変化していない。そして変化するチャンスも所帯人数の減少と、自動車の買い替えに伴う省エネ化が進んだこと以外に変化はない。
ガス会社でエネルギー設備の商品企画・営業を担当していたこともあり、当時の最先端の設備を設置した。ガス給湯暖房機で風呂・給湯とともに暖房は床暖房が主力である。その後、ガスファンヒーターとの組み合わせで台所のシステムキッチンに組み込んだガスレンジもすべて30年間稼働している。
仮に買い替えたとしても、省エネ性に大きな変化はないので、30年後、我が家のエネルギー消費構造は基本的に変化しない。もっとも、私は30年後は亡くなっているが、住宅も設備も現在と同水準である。再生可能エネルギーも自動車もわが家のエネルギー消費に大きな変化をもたらさないので、CO2排出削減に対して貢献しようもない。このことはどこの家庭、どこの事業所でも似たり寄ったりであることを示す。
つまり、2050年も化石燃料主体のエネルギー利用システムから脱却できないとすればどうあるべきか。最も経済性、環境性、燃料調達可能性の高い化石燃料、つまりLNG・シェール革命によるLNGを最優先に利用するシステムにしかなりえないのである。
このあたりの再生可能エネルギー神話・信仰・願望についての考え方は、社会一般の通念からかけ離れているので、今後も繰り返し情報発信していくが、本質は変わらない。
